
物件管理
PROPERTY MANAGEMENT
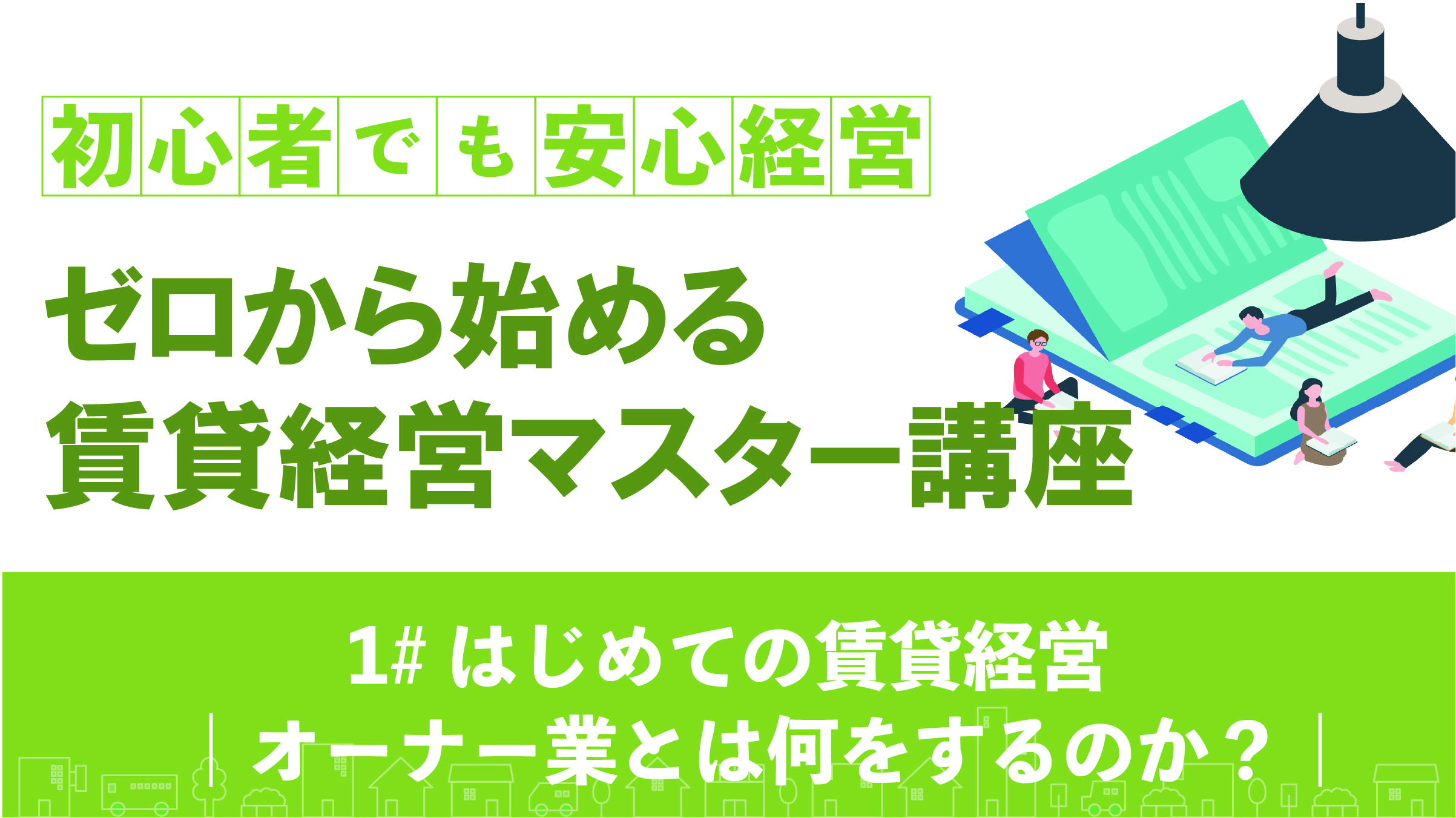
はじめての賃貸経営|オーナー業とは何をするのか?
「不動産投資で家賃収入を得たい」「相続したアパートを活用したい」——そんな理由から、これから賃貸経営を始めようと考えている方は少なくありません。
詳しく見る
近年は副業や資産形成の手段として「不動産投資」「オーナー業」が注目されていますが、その実態をよく理解せずに始めてしまうと、後々トラブルや赤字に悩まされることになります。
賃貸経営は「家を貸して家賃をもらう」だけの簡単な仕組みではありません。オーナーは入居者募集から契約、家賃管理、建物の維持管理、税務申告まで幅広い業務を担う“経営者”です。
本記事では、これから賃貸経営を始める方に向けて、オーナー業の全体像を整理し、基本的な役割や流れを解説します。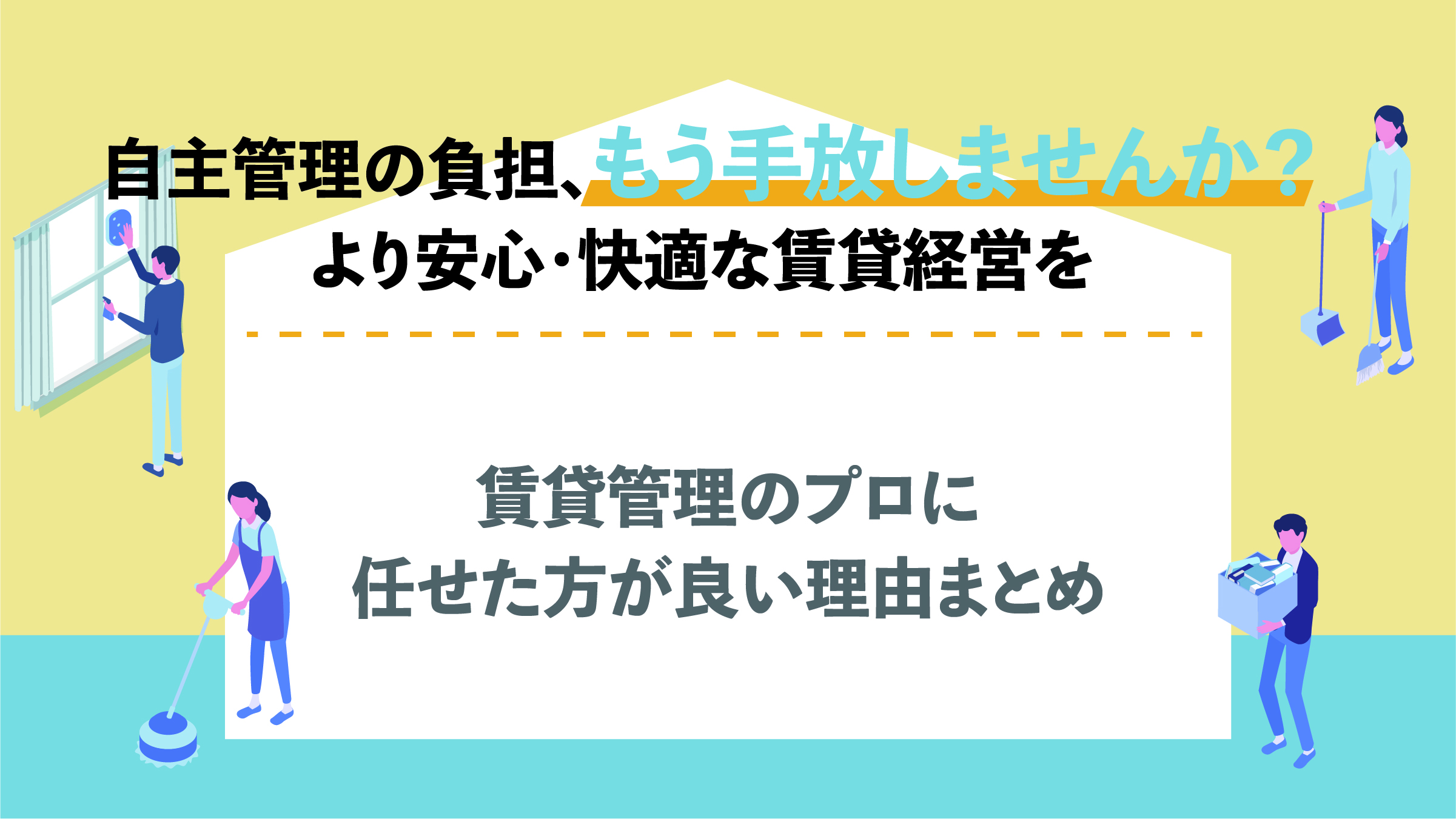
賃貸管理のプロに任せた方が良い理由まとめ
自主管理で賃貸経営をしているオーナーの中には、「自分でやればコストがかからない」と思っている方も多いでしょう。
詳しく見る
しかし、賃貸経営には家賃滞納、空室、原状回復、法改正対応、設備トラブル など、専門知識と時間が求められる業務が山積しています。
本記事では、これまで9本の記事で解説してきた内容を踏まえ、なぜ賃貸管理のプロに任せた方が良いのかを総合的に整理し、オーナーにとってのメリットを詳しく解説します。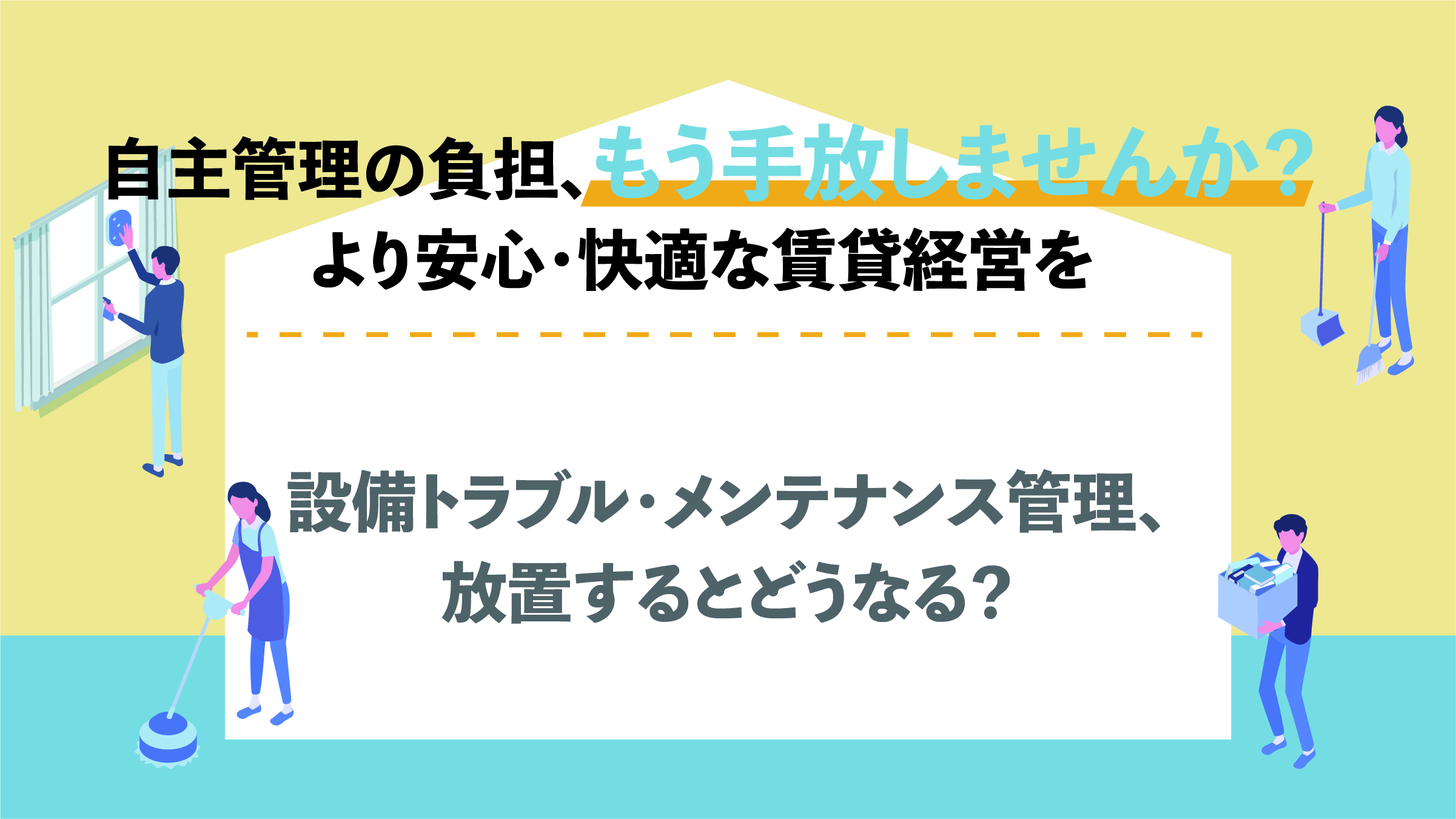
設備トラブル・メンテナンス管理、放置するとどうなる?
賃貸経営において、設備トラブルや日常的なメンテナンスは避けられない課題です。
詳しく見る
しかし、自主管理オーナーの中には「問題が起きてから対応すればよい」と後回しにしてしまう方も少なくありません。
放置すると、入居者の信頼低下、早期退去、建物の劣化、法的リスク など、賃貸経営に深刻な影響が出ます。
本記事では、設備トラブルやメンテナンス管理の重要性、放置した場合のリスク、そして管理会社に任せるメリットを詳しく解説します。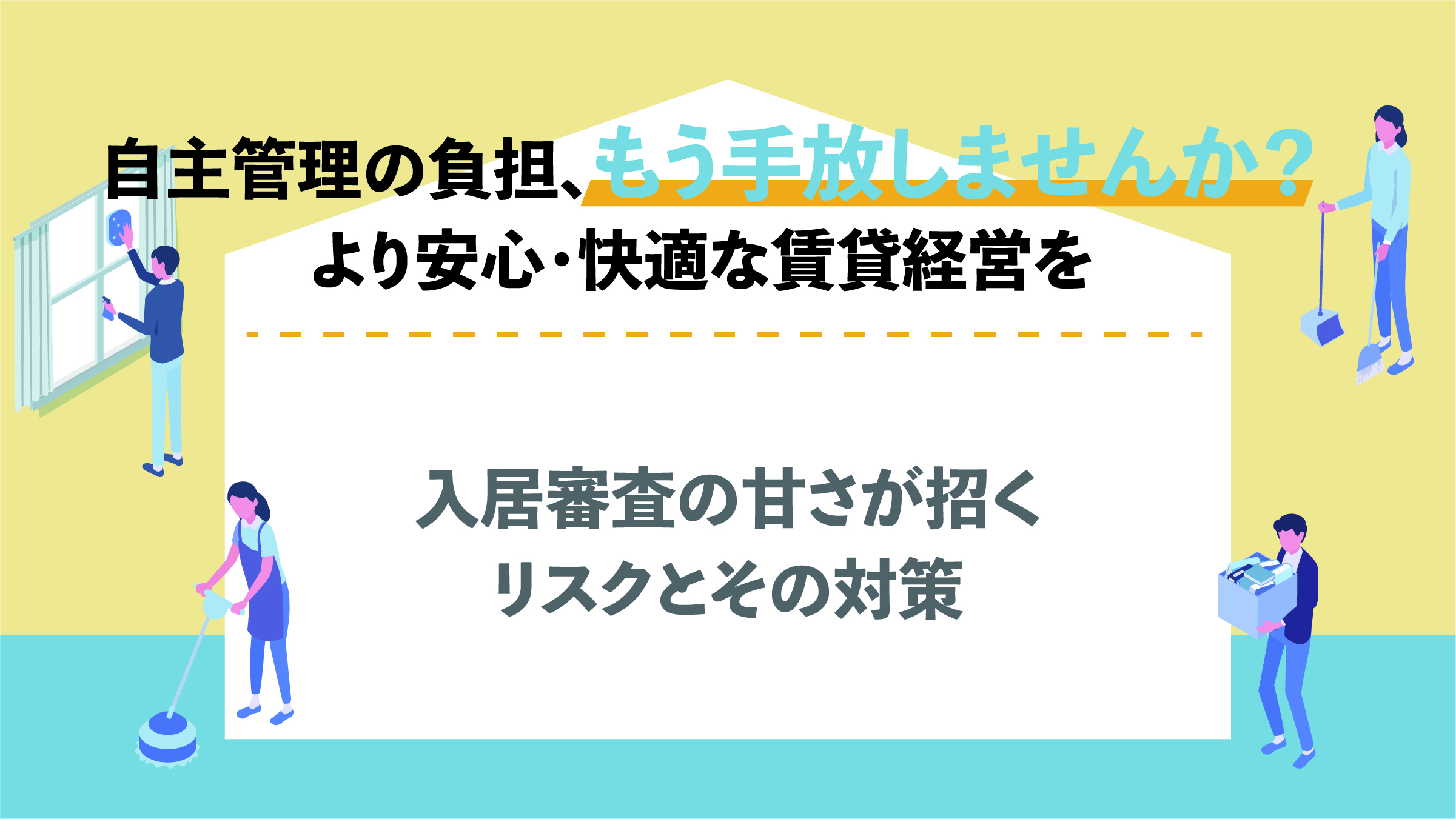
入居審査の甘さが招くリスクとその対策
賃貸経営において、入居審査はオーナーの収益とトラブル防止の根幹です。
詳しく見る
しかし、自主管理で運営していると「とりあえず入居させてしまった」という甘い審査を行いがちです。その結果、家賃滞納や設備破損、近隣トラブルといった深刻なリスクを招くことがあります。
本記事では、自主管理オーナーが陥りやすい入居審査を甘くしてしまったことによる具体的なリスク、そして管理会社を活用した安全な入居審査の方法を詳しく解説します。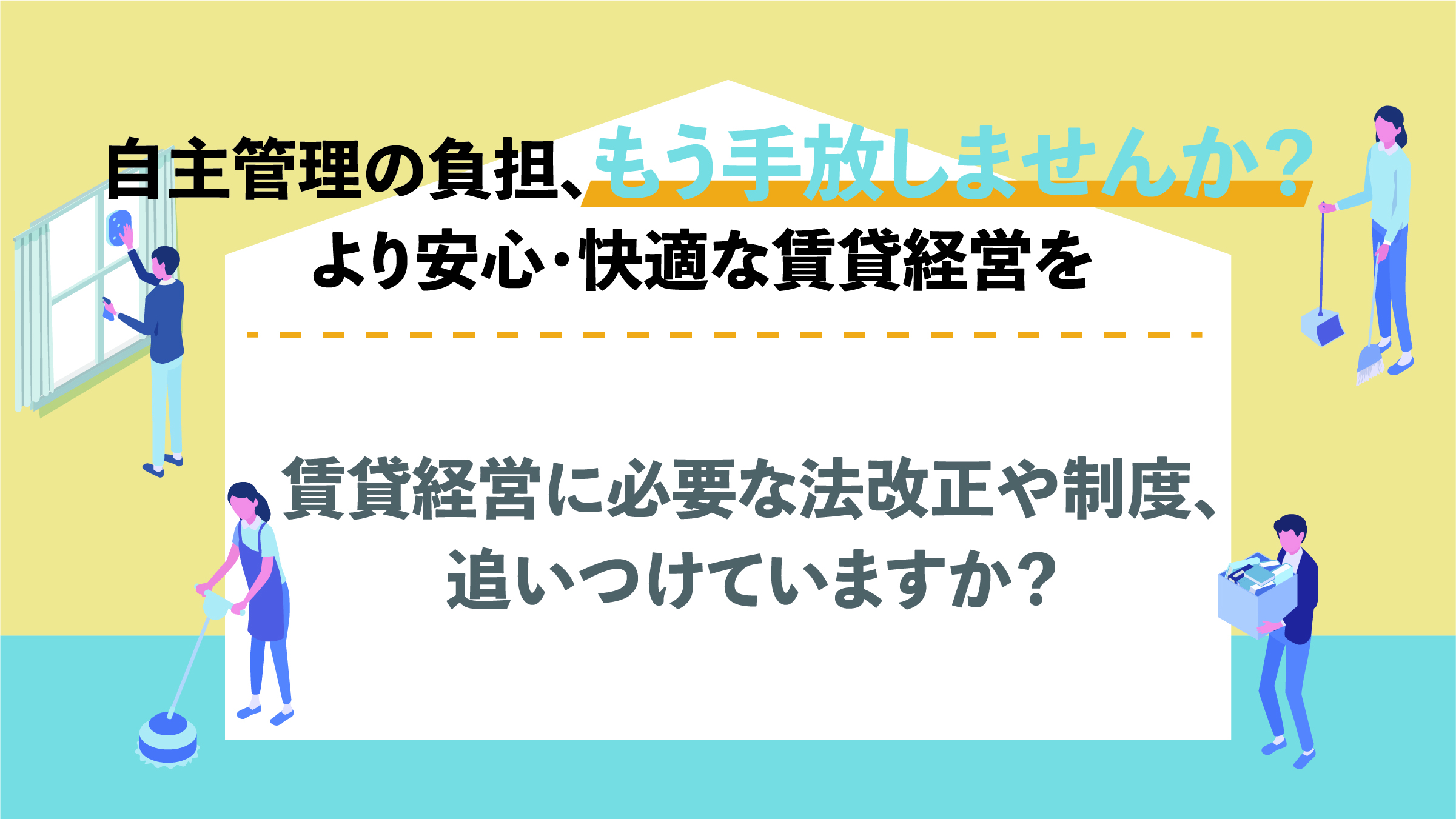
賃貸経営に必要な法改正や制度、追いつけていますか?
賃貸経営を自主管理で行っているオーナーの多くが見落としがちなポイント
詳しく見る
──それが 法改正や制度変更への対応 です。
民法改正や宅建業法の改正、入居者保護に関する制度などは数年単位で更新されており、知らずに従来通りの管理をしていると、知らぬ間に違法状態や入居者とのトラブルに発展するリスクがあります。
本記事では、自主管理オーナーが押さえておくべき最新の法改正・制度の概要と、対応を怠った場合のリスク、そして管理会社に任せることで得られる安心について詳しく解説します。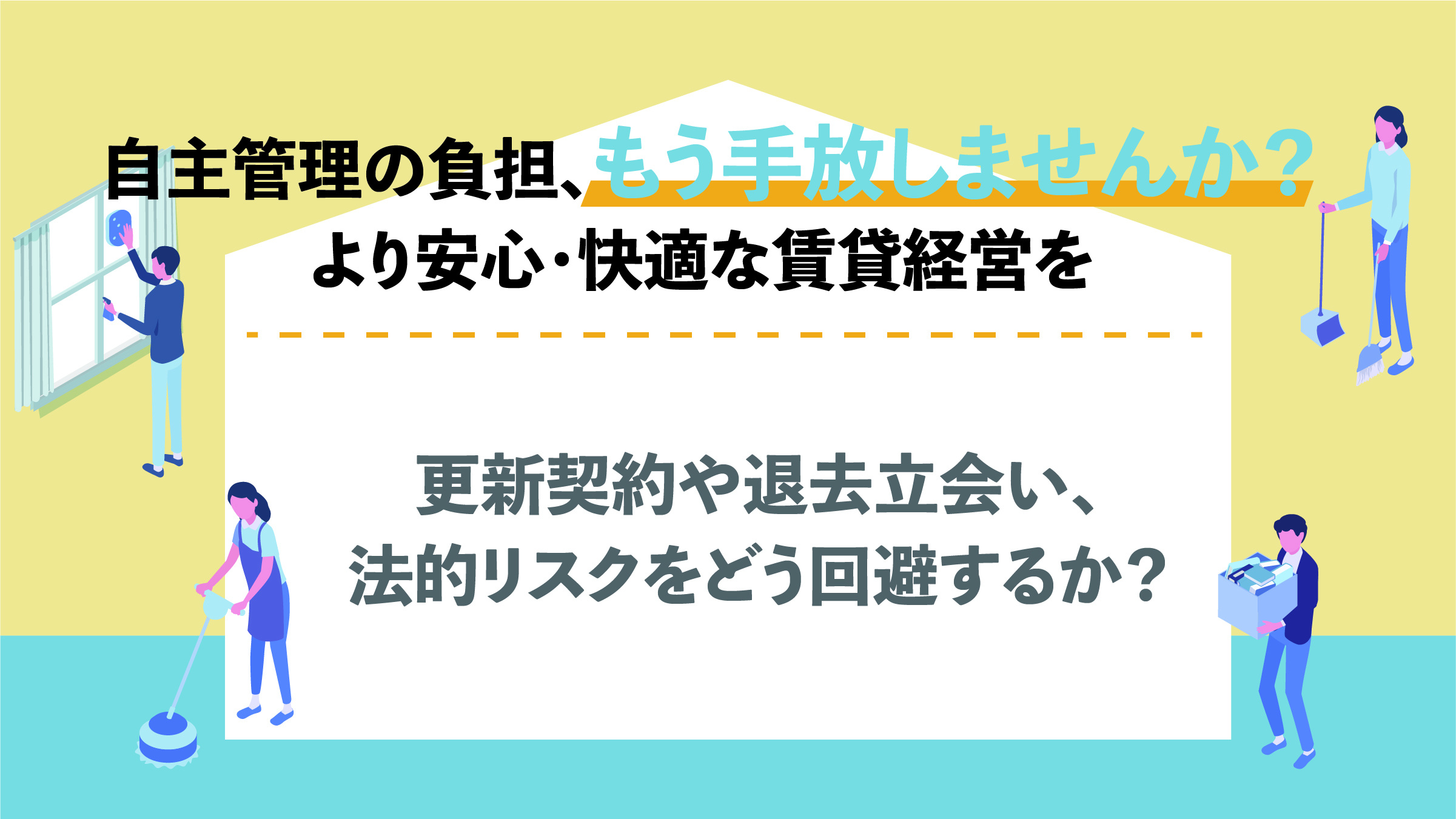
更新契約や退去立会い、法的リスクをどう回避するか?
自主管理で賃貸経営をしているオーナーにとって、「契約更新」と「退去立会い」は避けて通れない重要業務です。
詳しく見る
しかし、ここでの対応を誤ると 法的トラブルや金銭的損失に直結します。
「更新料を請求できる?」「退去立会いで原状回復費用をどう分担する?」──こうした疑問を放置すると、入居者との紛争や裁判リスクが高まります。
本記事では、自主管理オーナーが直面しやすい更新契約と退去立会いの課題、その法的リスク、そして管理会社を活用することで得られる安心について詳しく解説します。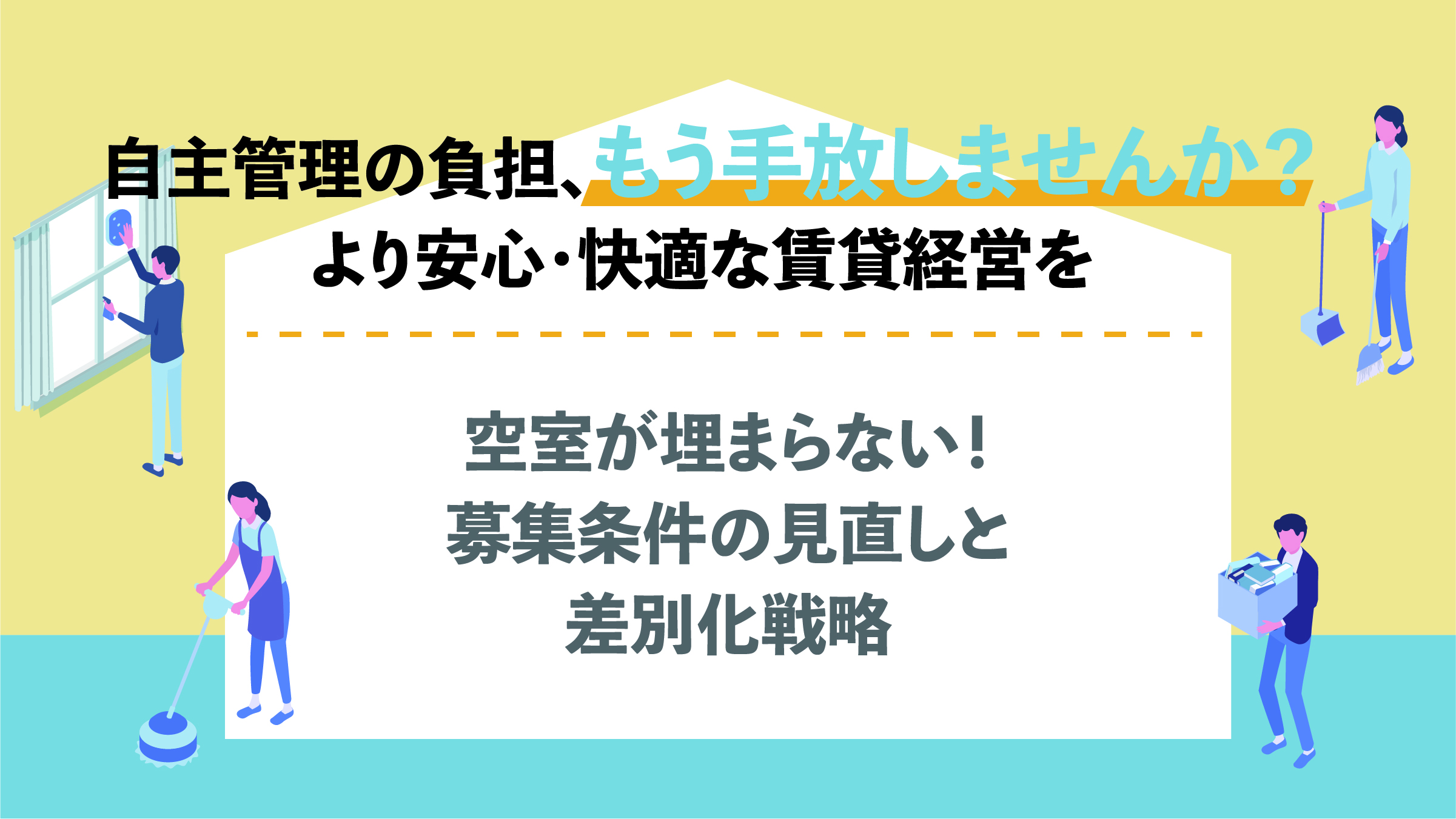
空室が埋まらない!募集条件の見直しと差別化戦略
自主管理のオーナーにとって「空室が長引くこと」は最大の悩みのひとつです。
詳しく見る
家賃を下げても反応がない、広告を出しても内見につながらない──そんな状況が続くと、毎月の収益は大きく減少してしまいます。
本記事では、空室が埋まらない原因を整理し、自主管理オーナーが見直すべき募集条件や、競合物件との差別化戦略について徹底解説します。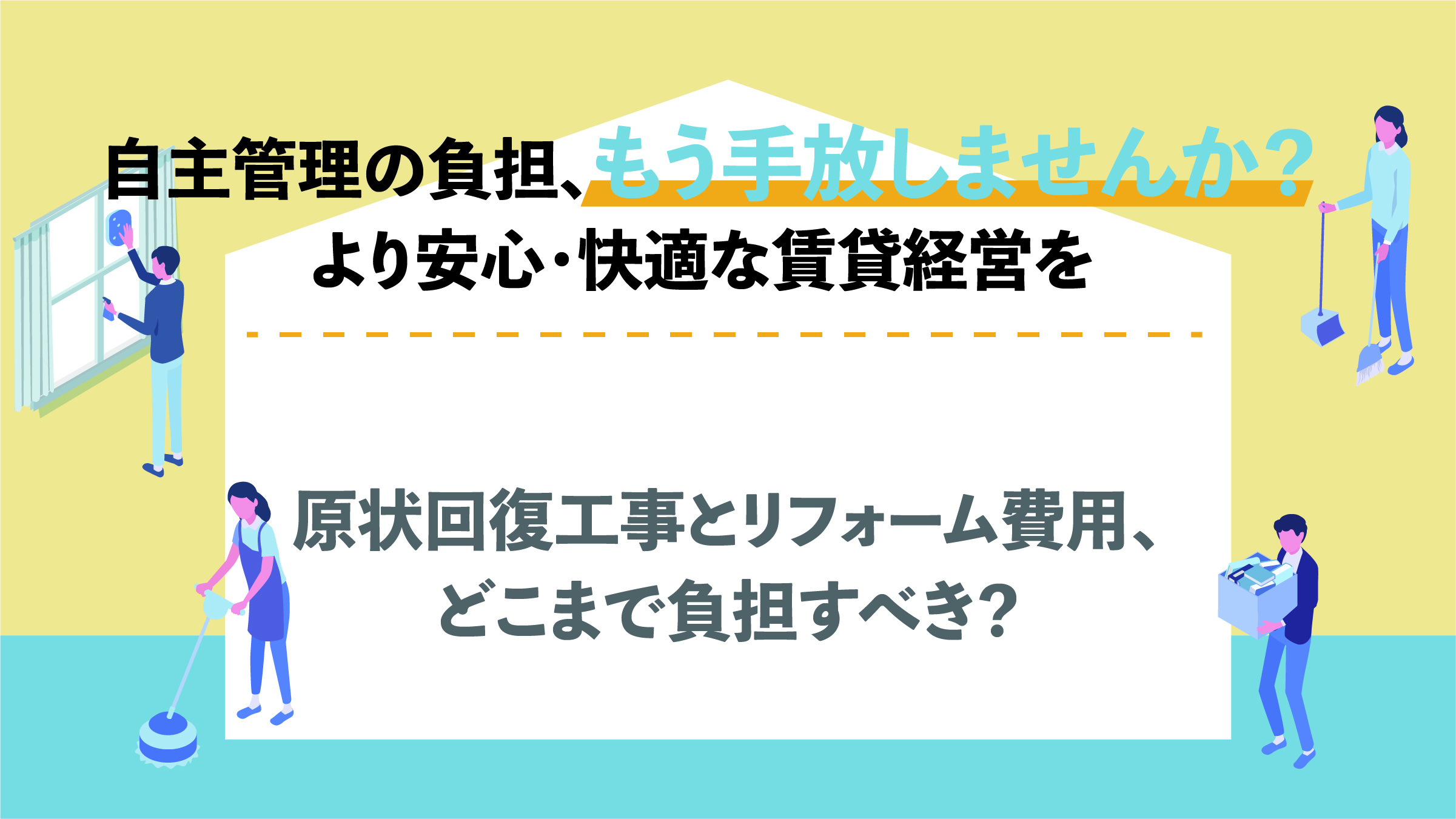
原状回復工事とリフォーム費用、どこまで負担すべき?
賃貸物件を自主管理しているオーナーにとって、入居者が退去した後の「原状回復工事」は大きな悩みどころです。
詳しく見る
「どこまでを入居者負担にできるのか?」「リフォーム費用はオーナーが全額負担しないといけないのか?」──この判断を誤ると、入居者とのトラブルに発展し、最悪の場合は裁判にまで至るケースもあります。
本記事では、国土交通省のガイドラインを踏まえ、自主管理オーナーが知っておくべき原状回復のルール、費用負担の境界線、リフォームを戦略的に行うポイントを徹底解説します。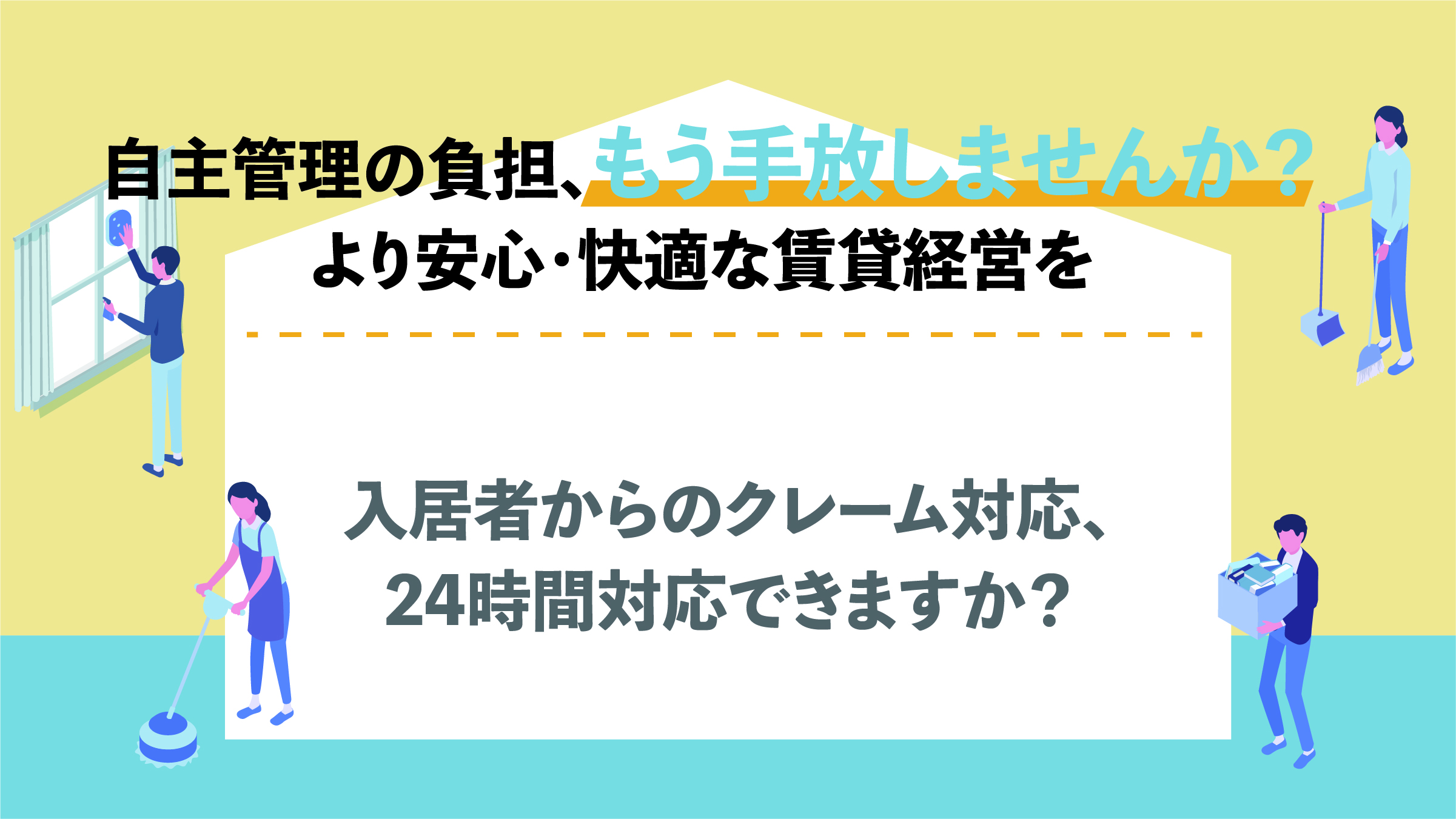
入居者からのクレーム対応、24時間対応できますか?
賃貸経営を自主管理で行っているオーナーにとって、入居者からのクレーム対応は避けられない課題です。
詳しく見る
「夜中に水漏れの電話がかかってきた」「隣人の騒音トラブルをどうすればいいかわからない」──こうした状況は、オーナーの生活や本業に大きな負担を与えます。
本記事では、自主管理オーナーが直面する典型的なクレーム事例と、その対応の難しさ、さらに管理会社に任せることで得られる安心とメリットを詳しく解説します。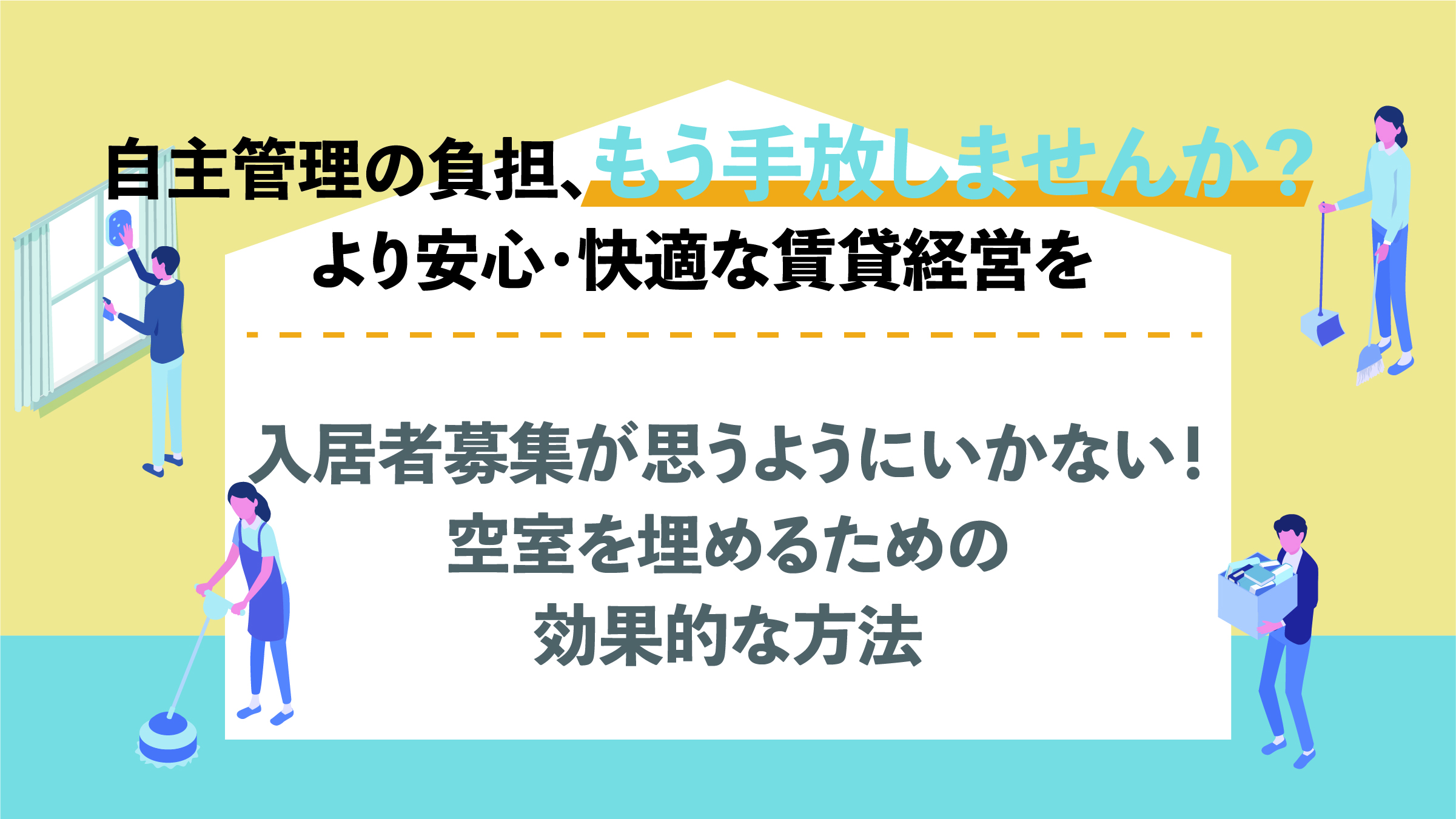
入居者募集が思うようにいかない!空室を埋めるための効果的な方法
賃貸経営を自主管理で行うオーナーにとって、頭を悩ませる大きな課題が「空室が埋まらない」問題です。
詳しく見る
「募集広告を出しているのに問い合わせがない」「内見はあるのに申込みにつながらない」など、空室期間が長引けば収益は大きく圧迫されます。
本記事では、自主管理オーナーが陥りやすい空室募集の失敗と、入居者を獲得するための効果的な方法、そして管理会社を活用するメリットを徹底解説します。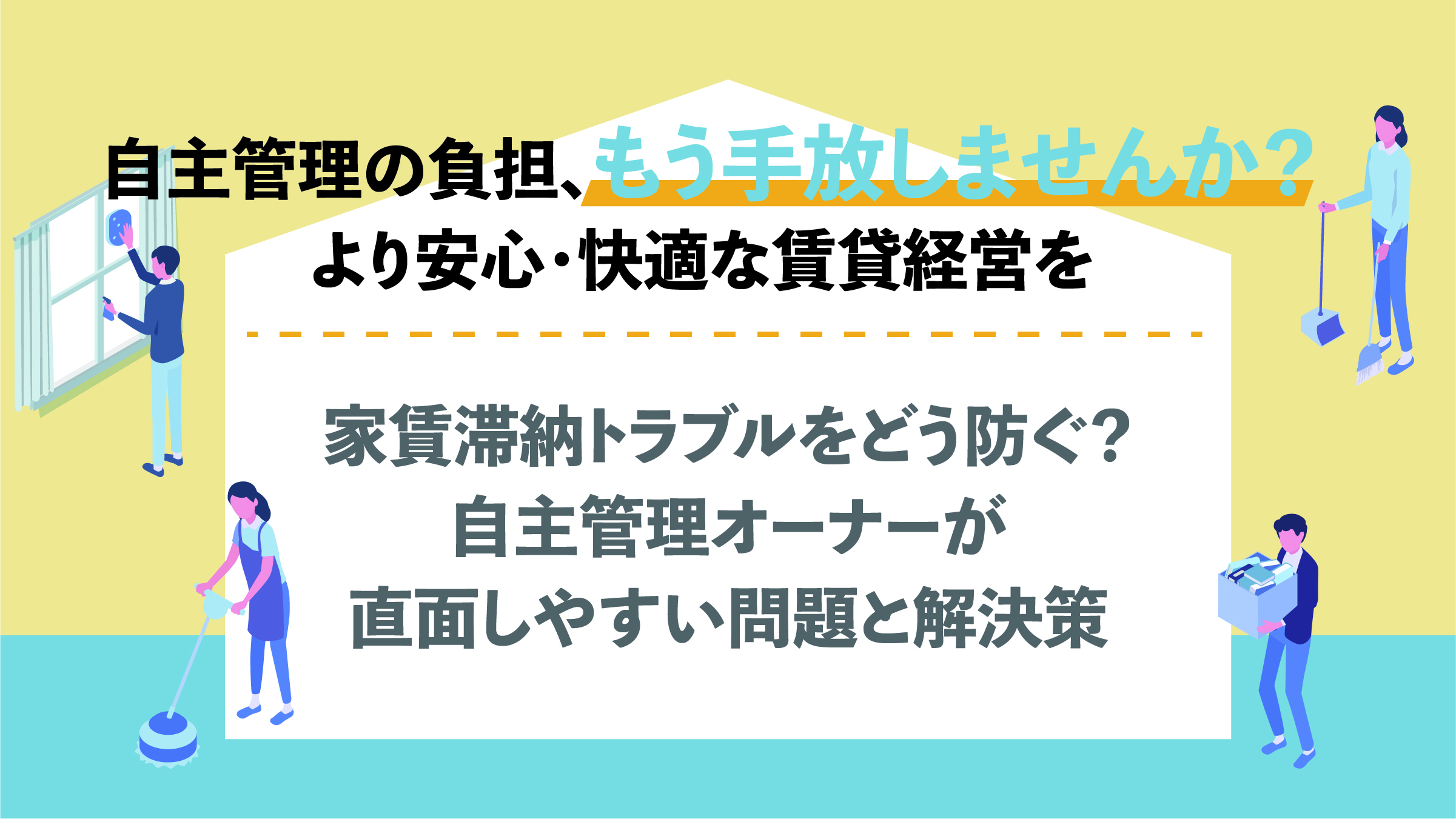
家賃滞納トラブルをどう防ぐ?自主管理オーナーが直面しやすい問題と解決策
賃貸経営を自主管理で行っているオーナーにとって、最も頭を悩ませる問題のひとつが「家賃滞納」です。入居者が家賃を支払わない場合、安定収益が揺らぐだけでなく、督促や法的手続きといった大きな負担がオーナーにのしかかります。実際、「滞納トラブルをきっかけに自主管理をやめて管理会社に委託した」という声も少なくありません。
詳しく見る
本記事では、自主管理オーナーが直面しやすい家賃滞納の問題点と、その解決策、さらに管理会社に任せることで得られるメリットを徹底解説します。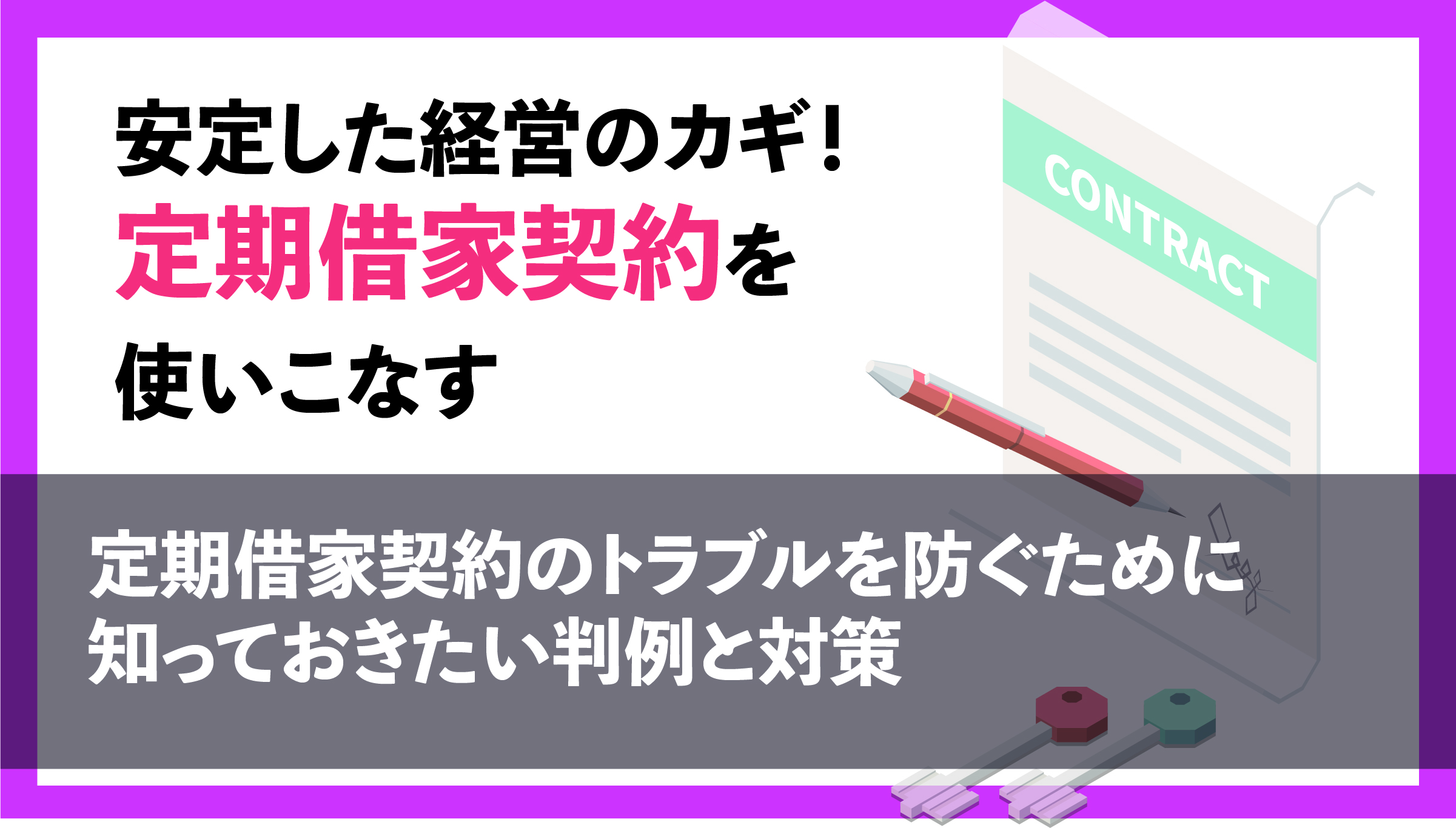
定期借家契約のトラブルを防ぐために知っておきたい判例と対策
定期借家契約は、契約期間が終了した時点で契約が自動的に終了する賃貸契約です。
詳しく見る
契約更新がないため、借主が契約期間終了後も居住を続けることはできません。
この契約形式は賃貸人と借主にとってメリットがありますが、その特性からトラブルも発生しやすいです。
定期借家契約に関する賃貸トラブルに関する7件の判例を一つずつ深堀りしていきます。各判例にはその背景、裁判所の判断、そしてその後の影響や実務上のアドバイスを加えて説明します。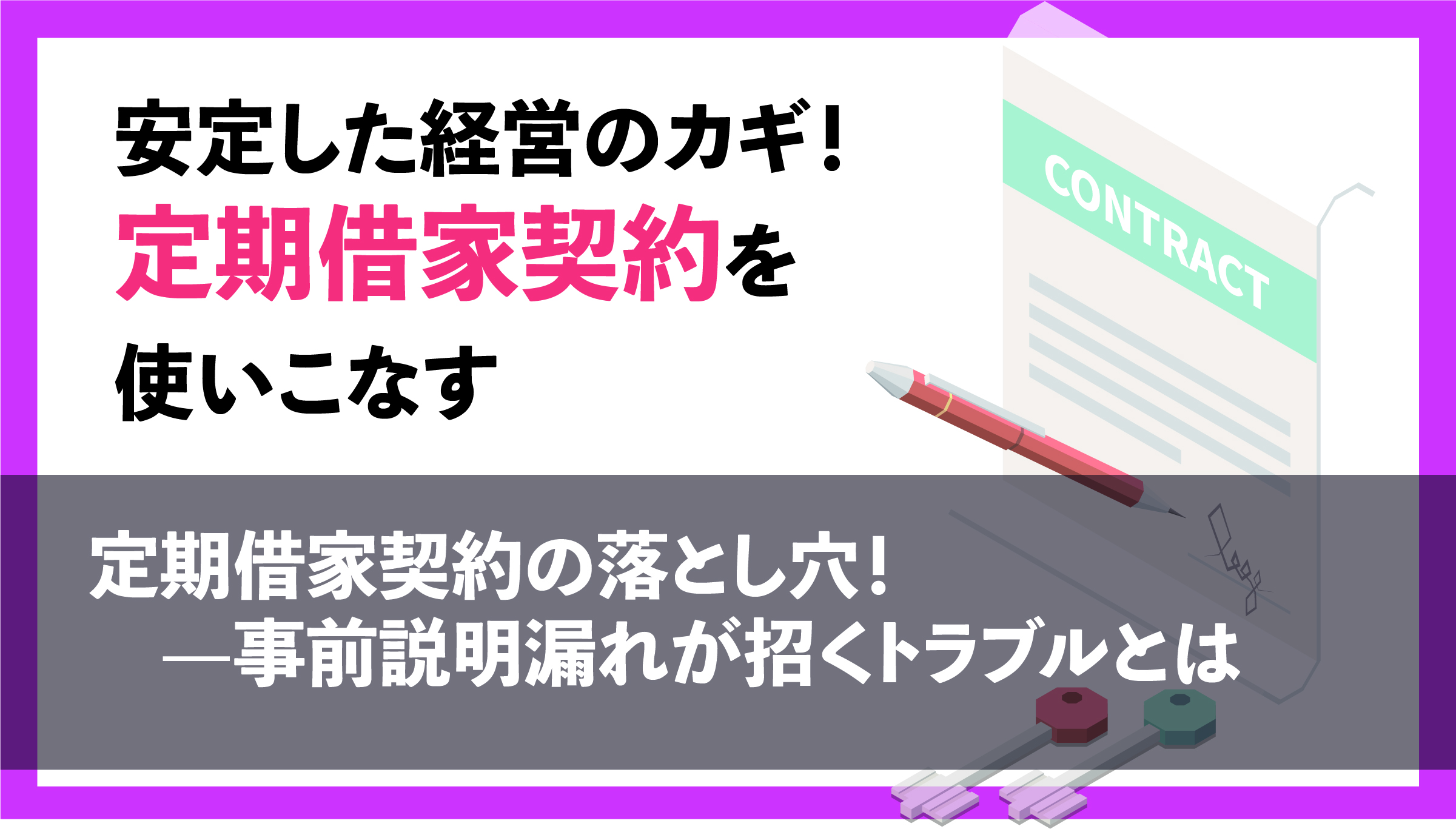
定期借家契約の落とし穴!事前説明漏れが招くトラブルとは
賃貸管理を行うオーナーにとって、「空室リスクの低減」と同じくらい重要なのが、契約トラブルの未然防止です。特に近年、一定期間で契約が終了する「定期借家契約」の活用が広がっていますが、正しい手続きを怠ると、思わぬトラブルに巻き込まれる危険性があります。
詳しく見る
この記事では、実際のトラブル事例をもとに、定期借家契約における「事前説明」の重要性と、賃貸管理上注意すべきポイントを徹底解説します。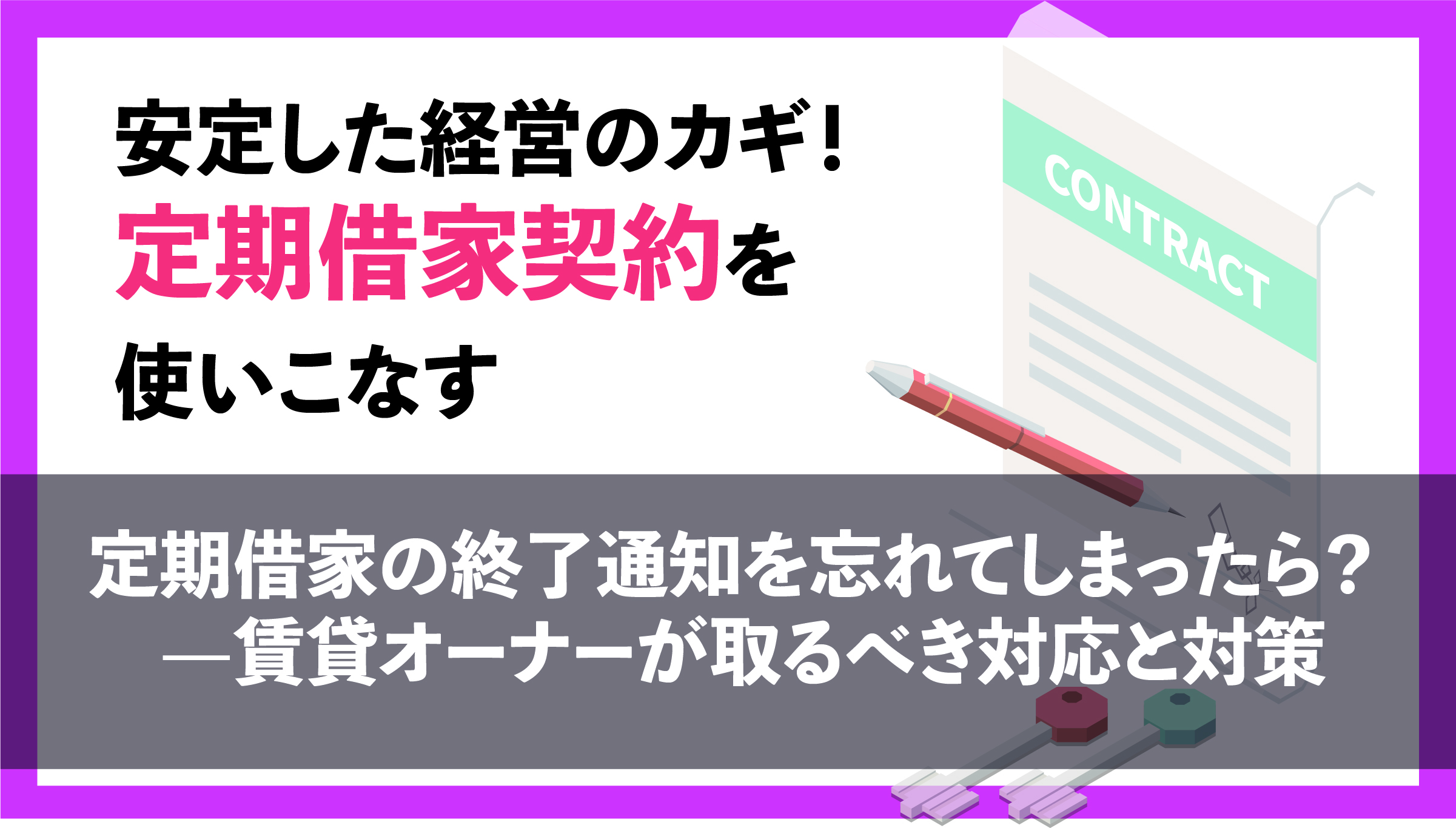
定期借家の終了通知を忘れてしまったら?賃貸オーナーが取るべき対応と対策
賃貸管理を行うオーナーにとって、定期借家契約は空室リスクやトラブル防止に有効な手段のひとつです。しかし、終了通知を忘れてしまった場合、思わぬリスクを招くことになります。
詳しく見る
この記事では、
* 定期借家契約の基本
* 終了通知を忘れた場合に起きること
* オーナーが取るべき具体的対応策
* 再発防止のための管理ポイント
を詳しく解説します!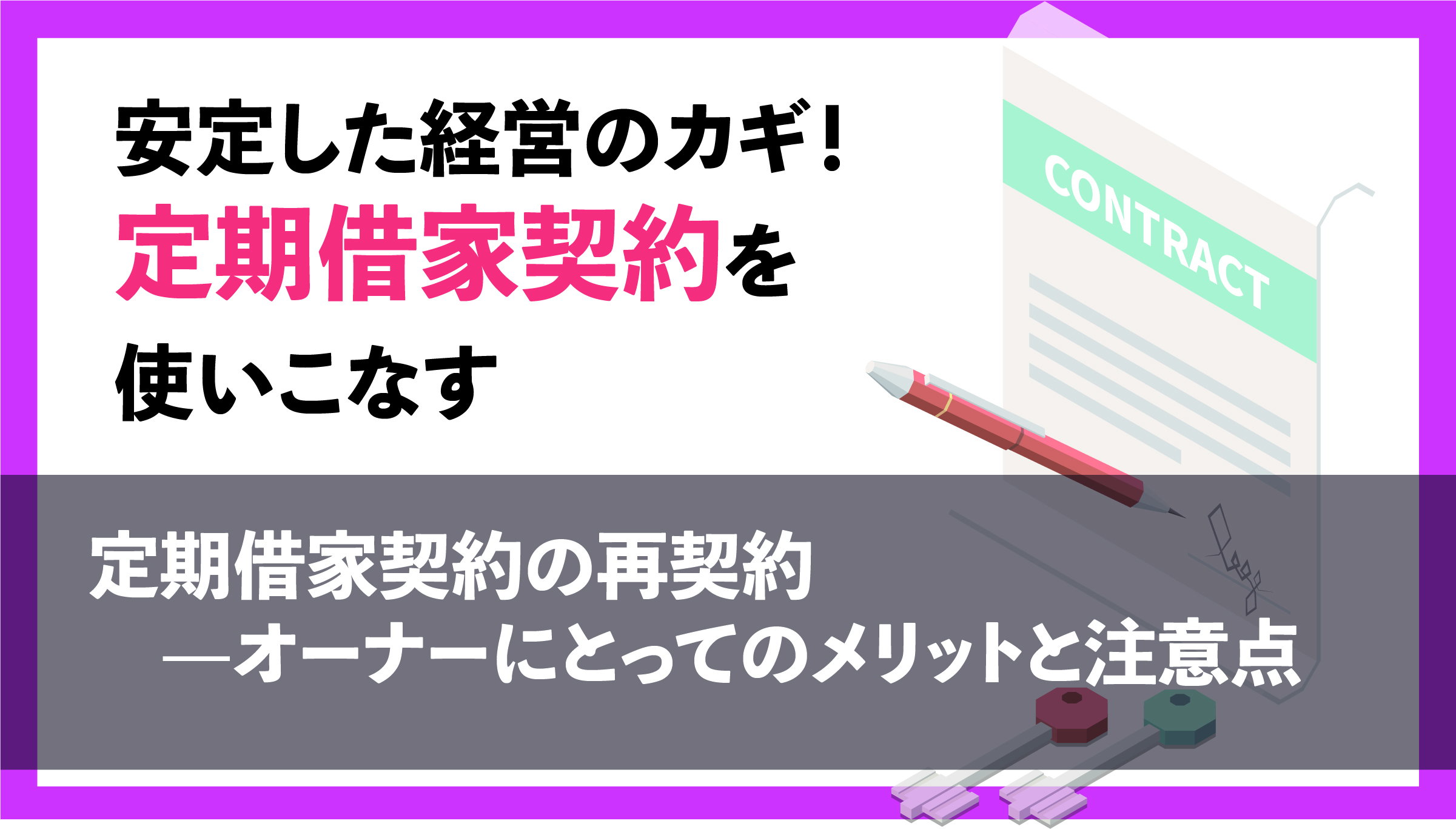
定期借家契約の更新後の再契約—オーナーにとってのメリットと注意点
定期借家契約はその特性上、更新制度がないため契約期間終了後に借主が退去するのが原則です。しかし、契約終了後に借主が再契約を希望する場合、オーナーとしては新たな契約条件を設定した上で再契約する選択肢があります。ここでは、定期借家契約終了後における再契約について、オーナーとして知っておくべきメリットと注意点を解説します。
詳しく見る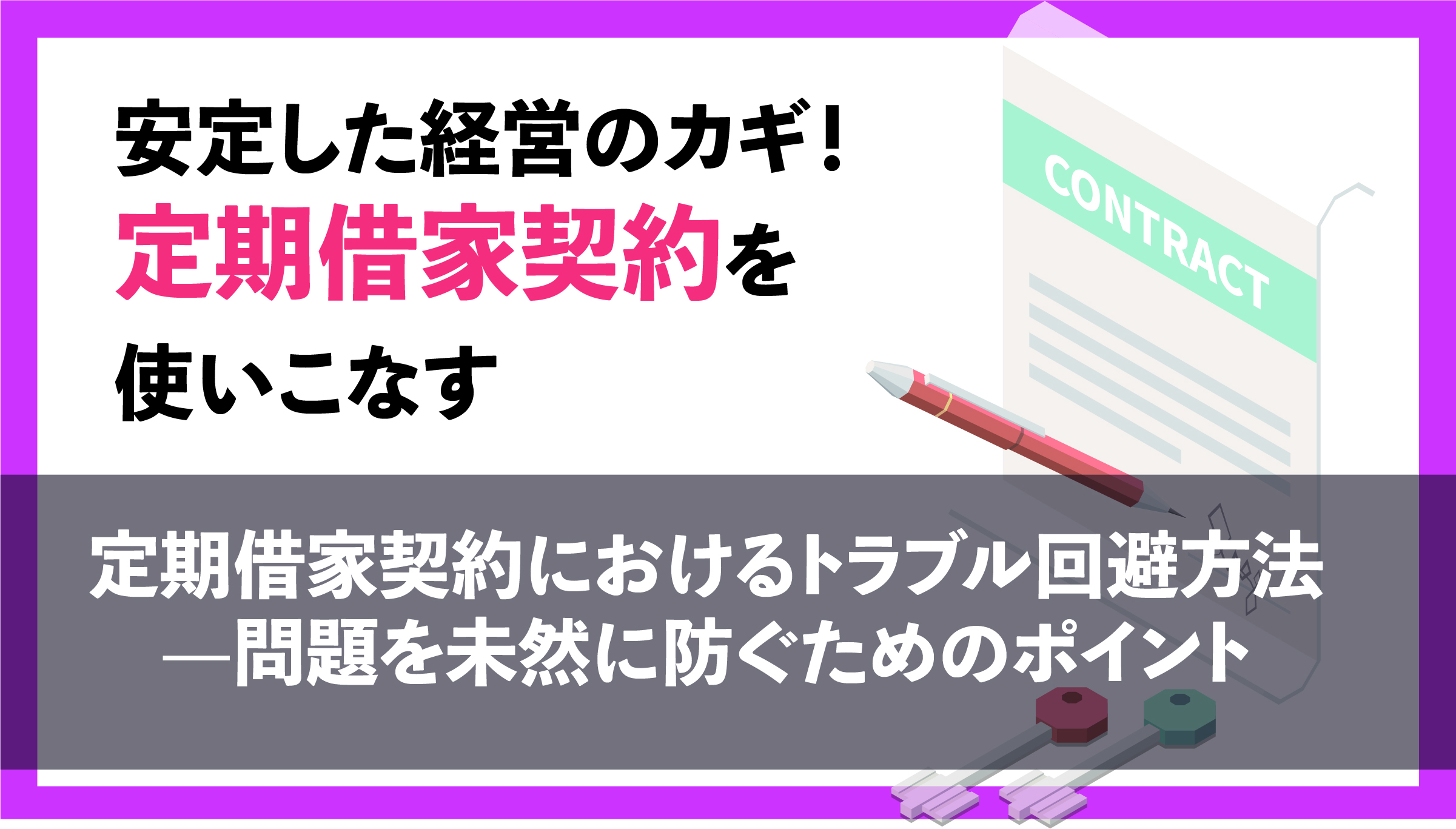
定期借家契約におけるトラブル回避方法—問題を未然に防ぐためのポイント
定期借家契約においては、借主とオーナーの間でさまざまなトラブルが発生する可能性があります。これらのトラブルを未然に防ぐためには、契約書の内容を明確にし、オーナーとして適切な対応を取ることが重要です。この記事では、定期借家契約における代表的なトラブル事例と、それらを回避するための具体的な対策について解説します。
詳しく見る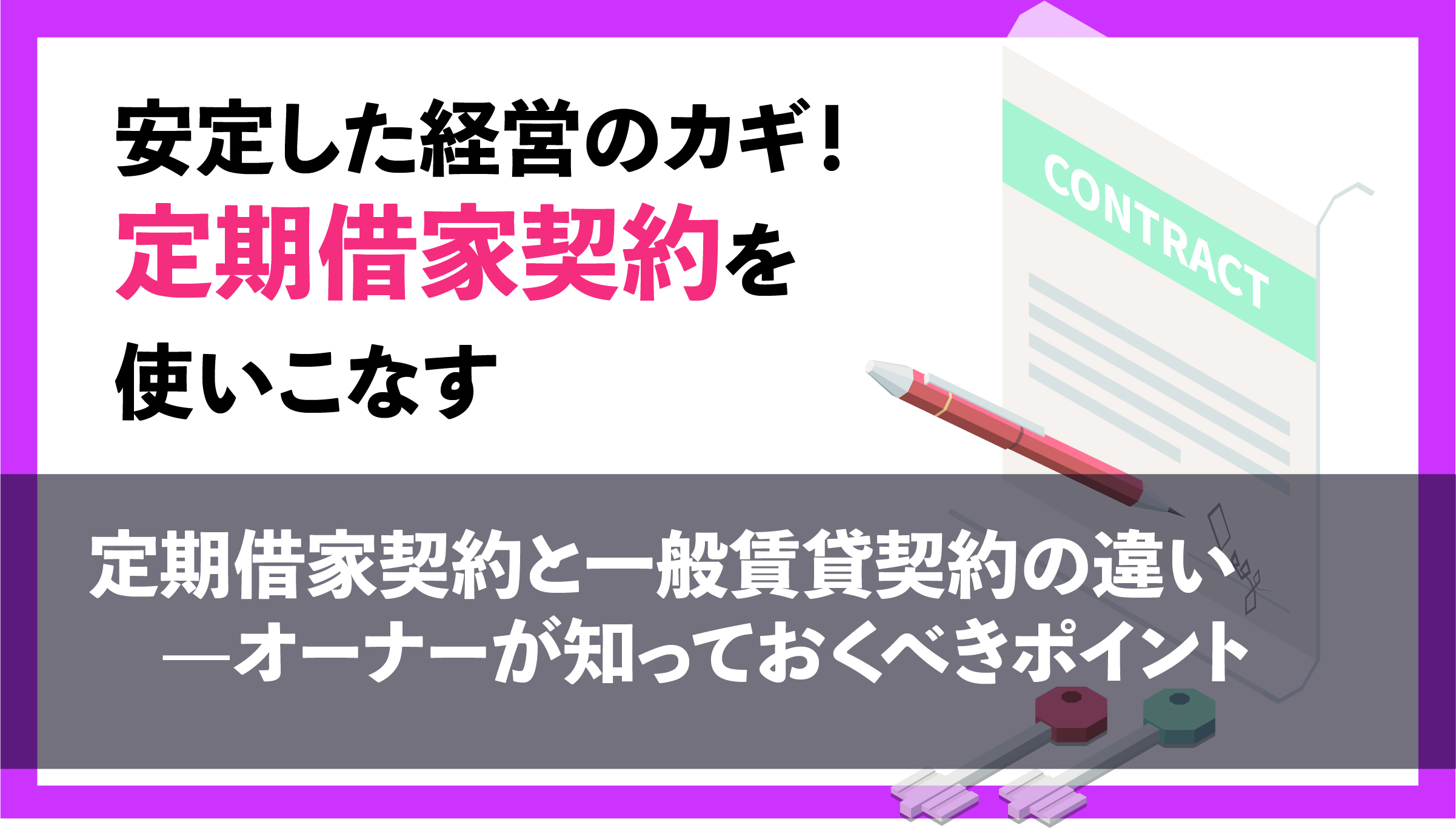
定期借家契約と一般賃貸契約の違い—オーナーが知っておくべきポイント
定期借家契約と一般的な賃貸契約(更新型契約)は、いくつかの重要な点で異なります。オーナーとしては、これらの違いをしっかりと理解しておくことが、賃貸経営を成功させるために不可欠です。本節では、定期借家契約と一般賃貸契約の違いについて解説し、それぞれの契約形態がもたらす利点と欠点を具体的に説明します。
詳しく見る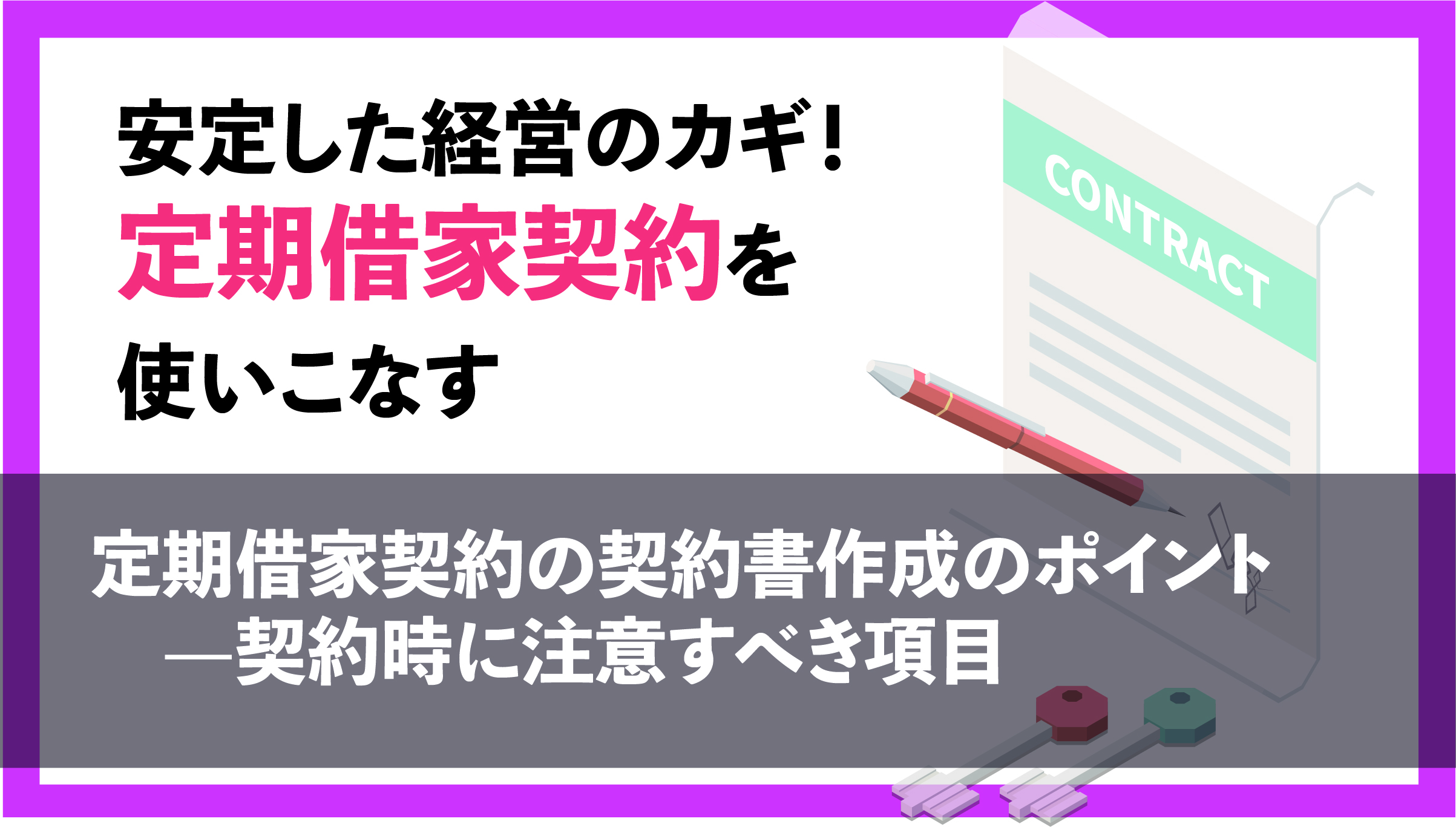
定期借家契約の契約書作成のポイント—契約時に注意すべき項目
定期借家契約を締結する際、契約書の作成は非常に重要な作業です。契約書は、将来のトラブルを未然に防ぐための重要な法的根拠となるため、慎重に取り扱わなければなりません。この記事では、定期借家契約書を作成する際に注意すべき主要なポイントについて詳しく説明します。
詳しく見る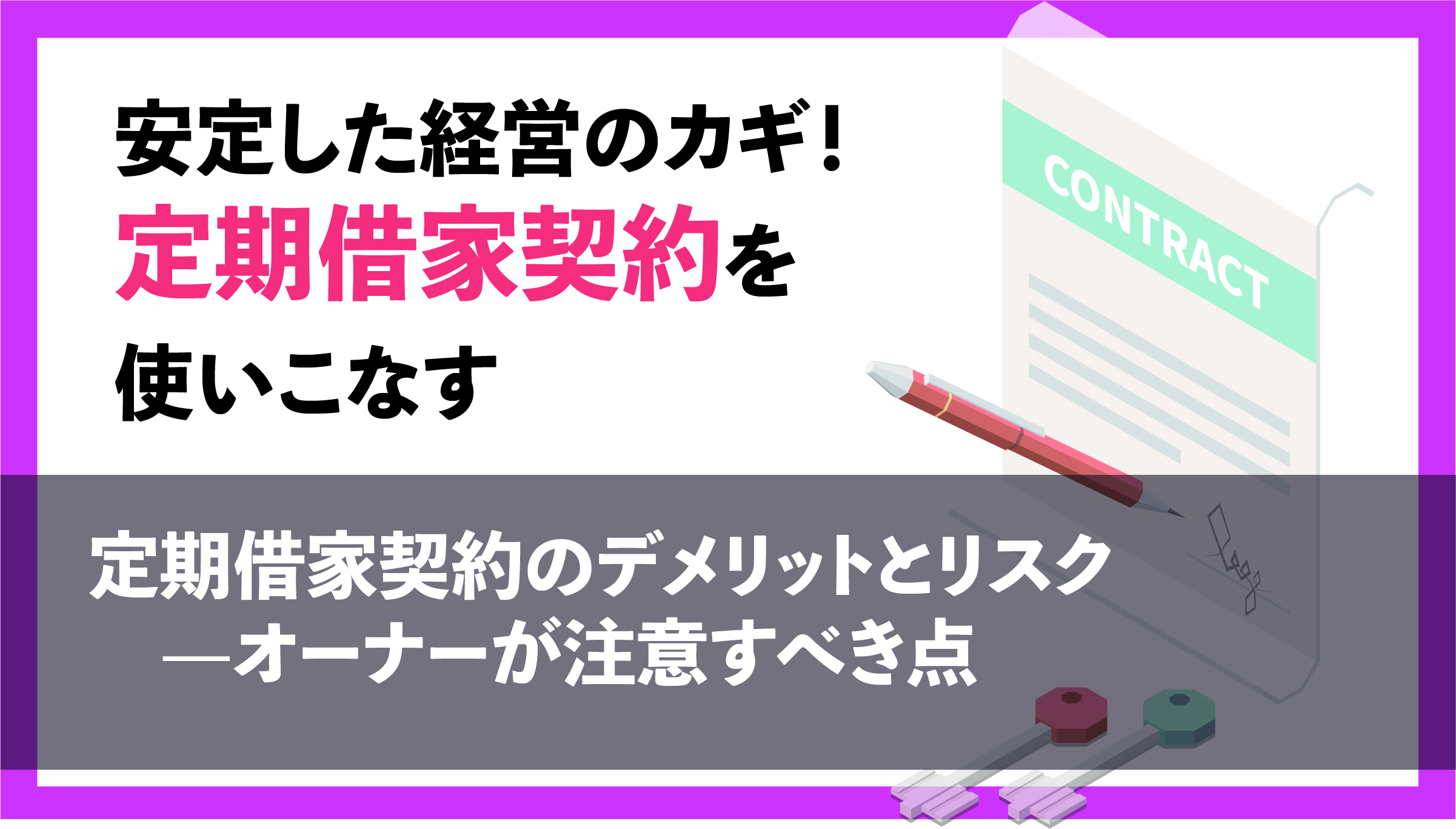
定期借家契約のデメリットとリスク—オーナーが注意すべき点
定期借家契約は賃貸オーナーにとってさまざまなメリットを提供しますが、その一方でデメリットやリスクも存在します。特に、契約期間終了後の取り決めや、借主との関係性に関して慎重に取り扱う必要があります。この記事では、定期借家契約のデメリットやリスク、そしてそれらを回避するためにオーナーが注意すべき点について詳しく解説します。
詳しく見る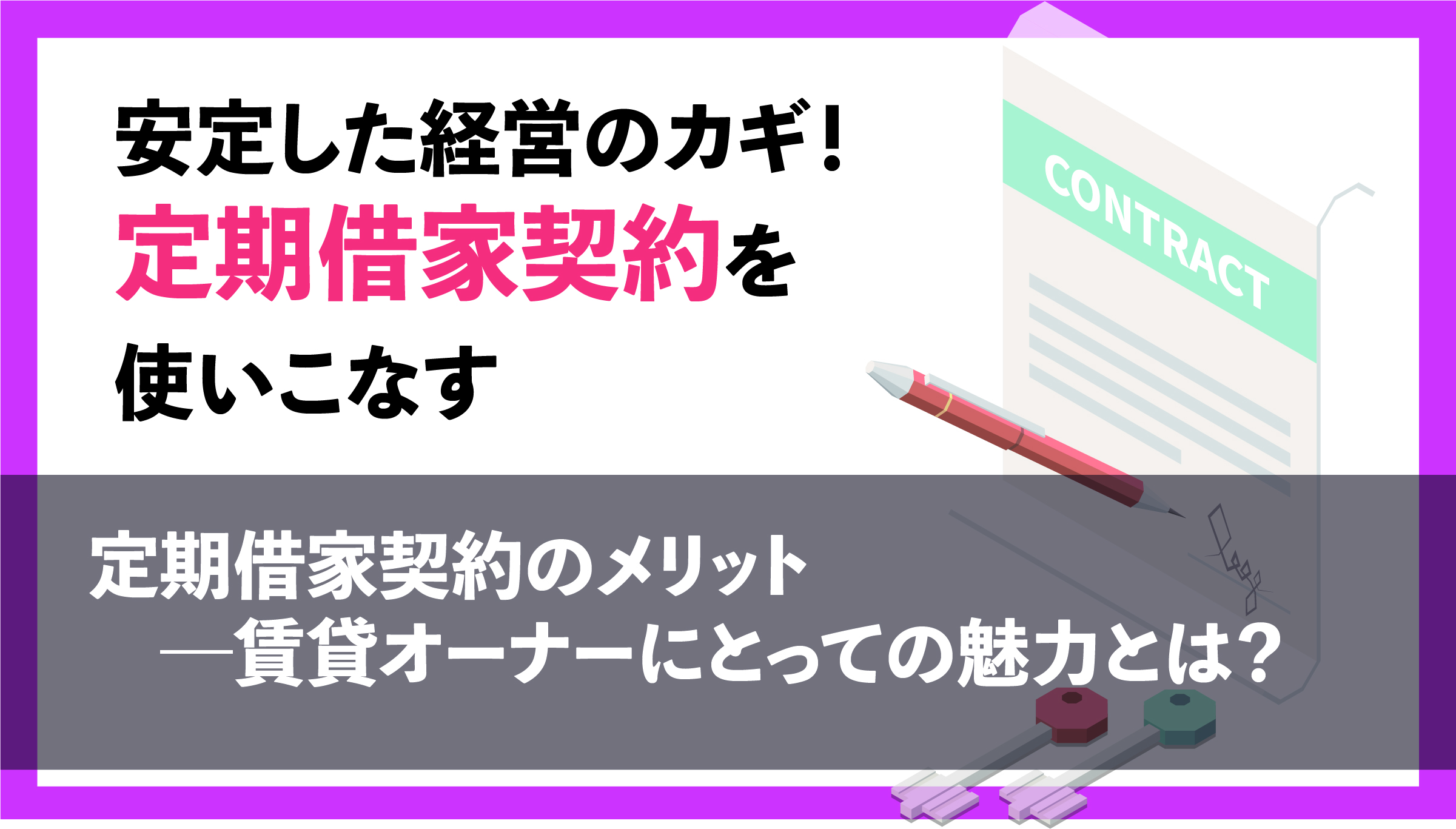
定期借家契約のメリット―賃貸オーナーにとっての魅力とは?
定期借家契約は、賃貸経営を行うオーナーにとってさまざまなメリットがあります。この契約形態を選択することで、オーナーは長期間にわたる安定した収益を得ることができ、また契約終了後に物件を自由に活用できるという特典もあります。この記事では、定期借家契約のメリットについて詳しく解説し、どのようにオーナーの利益に繋がるのかを具体的に説明します。
詳しく見る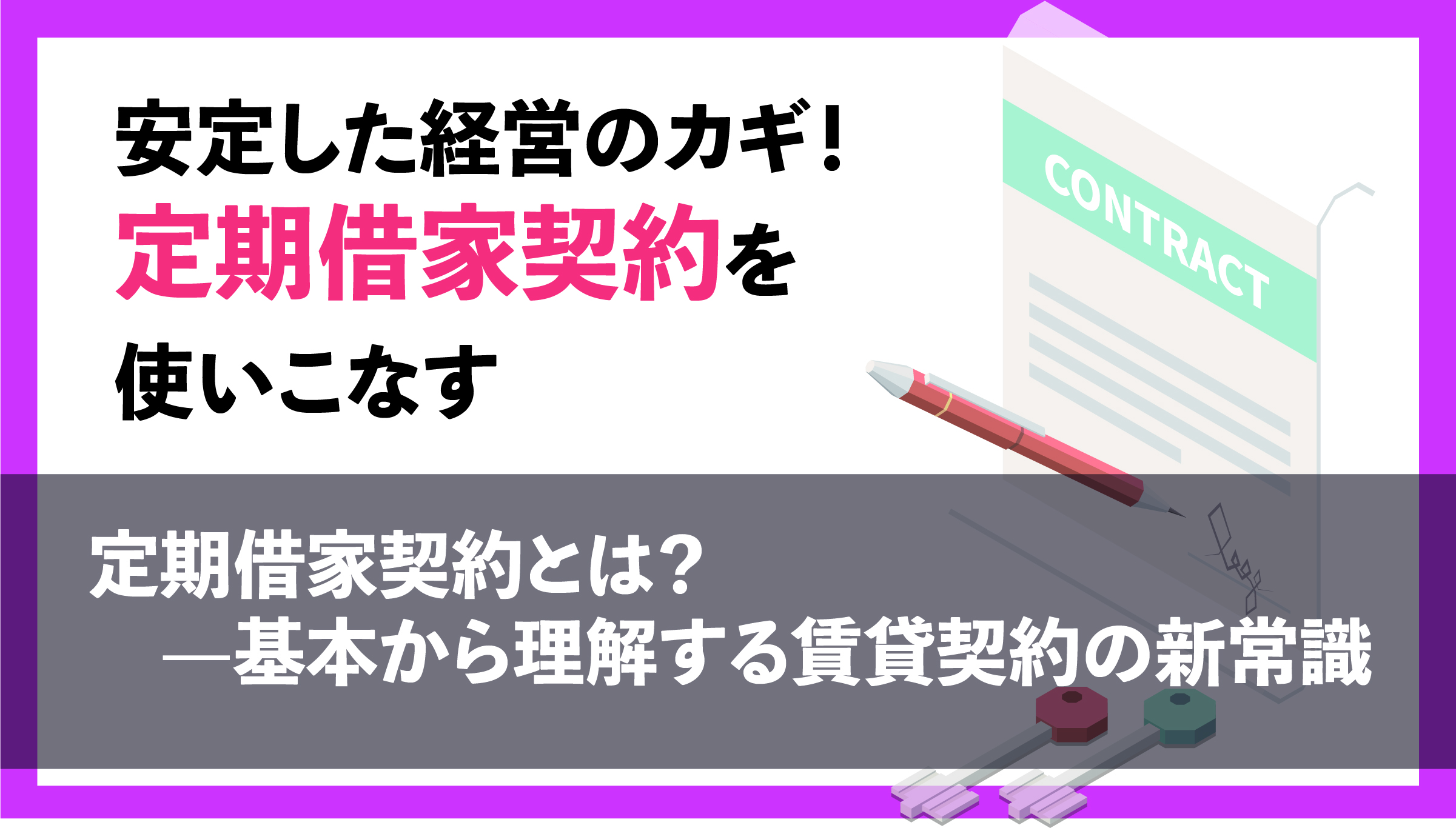
定期借家契約とは?—基本から理解する賃貸契約の新常識
賃貸経営を行っているオーナーにとって、賃貸契約の選択肢は重要です。その中でも、定期借家契約は、近年注目を集めている契約形態の一つです。この記事では、定期借家契約の定義、他の契約形態との違い、法律上の位置づけ、契約締結時に確認すべき重要な点、契約終了後の流れなどを詳しく解説し、実際に契約を結ぶ際に必要なポイントについても触れます。
詳しく見る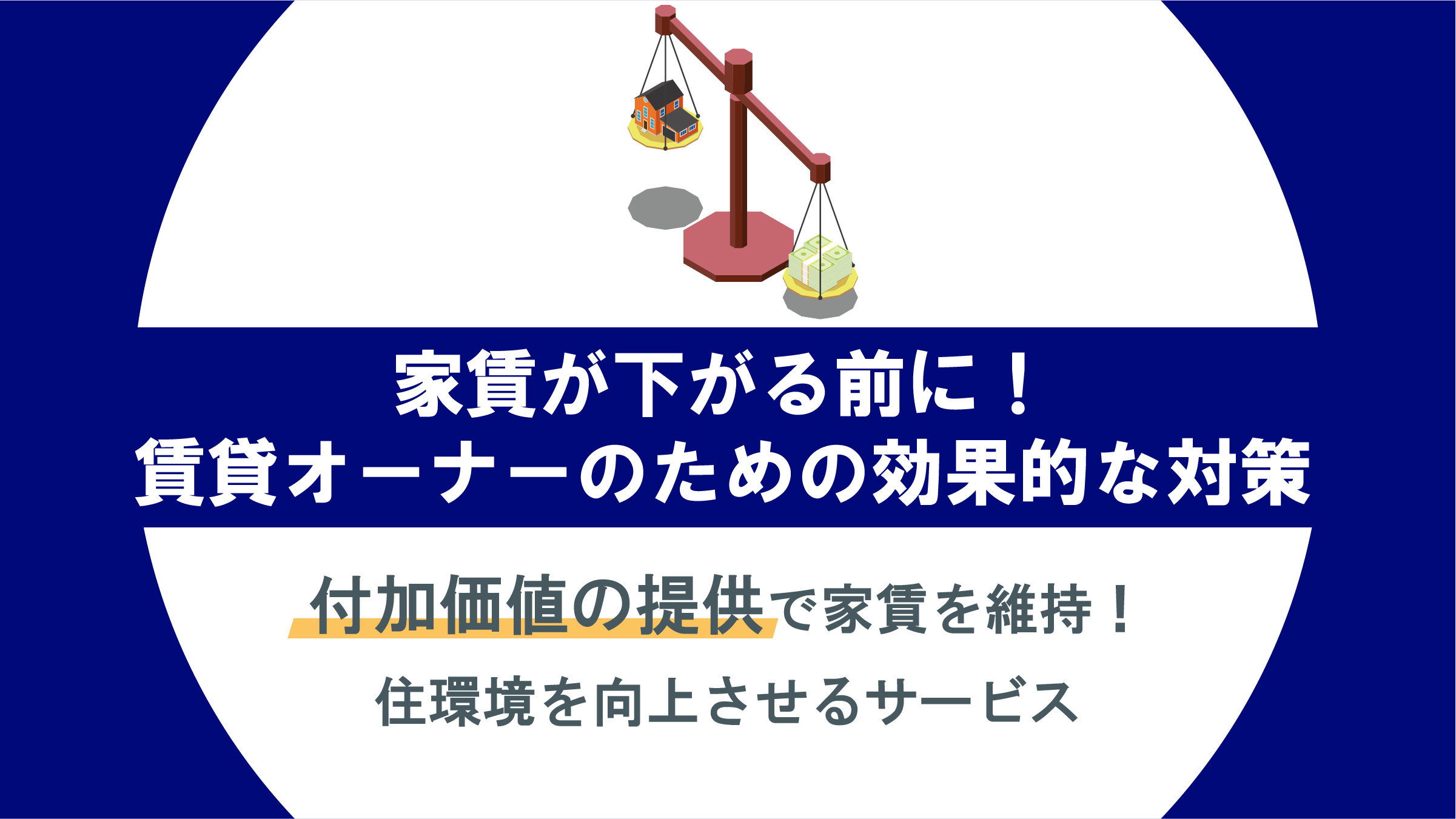
付加価値の提供で賃貸物件の家賃下落を防ぐ方法
賃貸物件の管理を行う大家さんや不動産オーナーにとって、家賃の下落は避けたい課題の一つです。特に市場の競争が激しく、供給過剰や景気の低迷が続く中で、家賃が下がると収益に大きな影響を及ぼします。そんな中で重要なのが、物件に「付加価値」を提供することです。付加価値を高めることで、家賃の下落を防ぎ、競争力を維持することが可能です。この記事では、賃貸物件に付加価値を提供する方法と、その実施に役立つ具体的な戦略を紹介します。
詳しく見る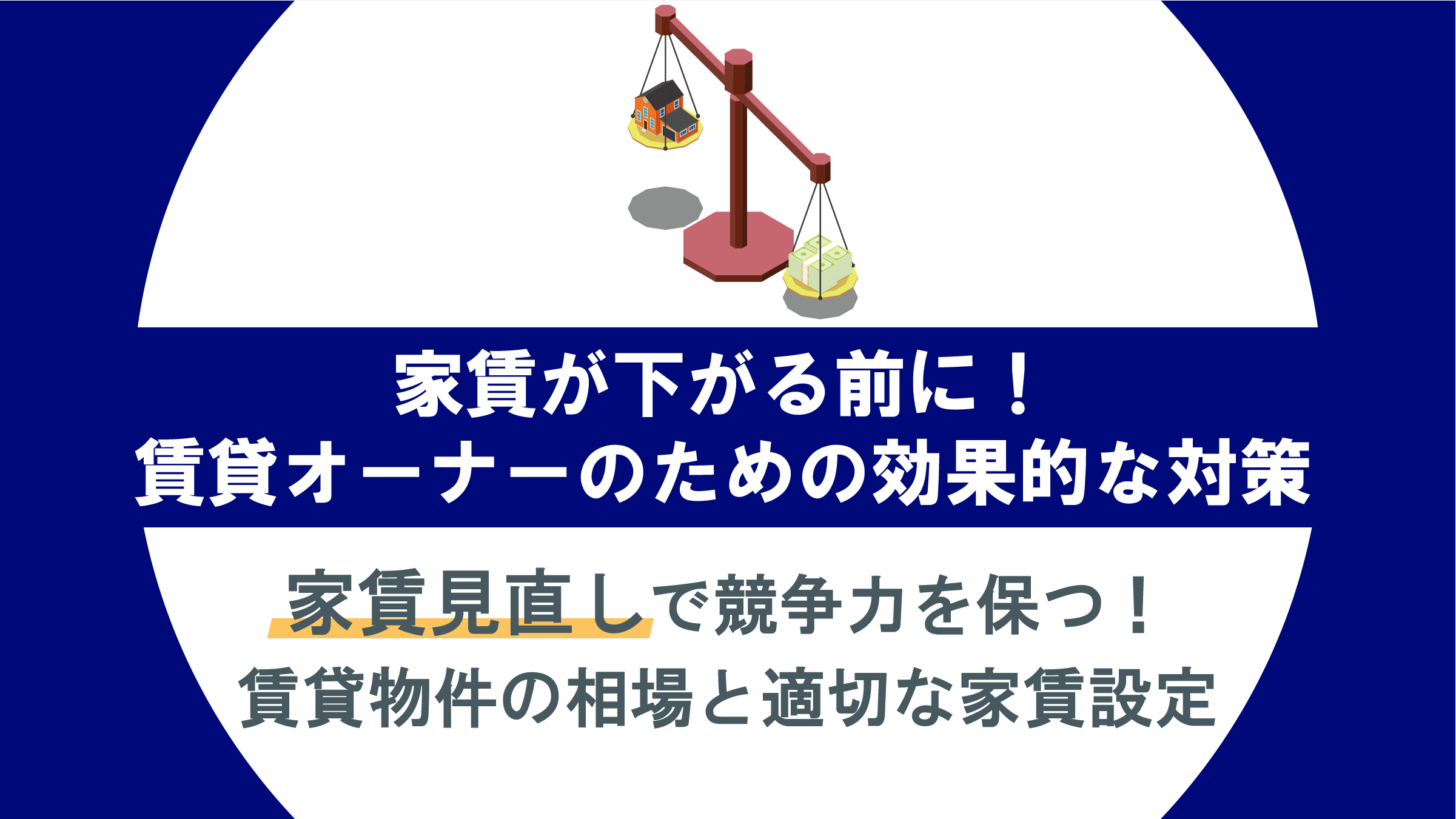
家賃見直しで競争力を保つ!賃貸物件の相場と適切な家賃設定
賃貸物件の管理をしている大家さんや不動産オーナーにとって、物件の家賃設定は非常に重要な要素です。家賃が高すぎると入居者が集まりにくく、低すぎると収益が減少します。物件が競争力を保つためには、適切な家賃設定が必要不可欠です。しかし、家賃は市場や周辺環境に影響されやすいため、定期的な見直しが欠かせません。
詳しく見る
この記事では、賃貸物件の家賃設定に関するポイント、賃貸相場の把握方法、そして競争力を保つための家賃見直しの重要性について解説します。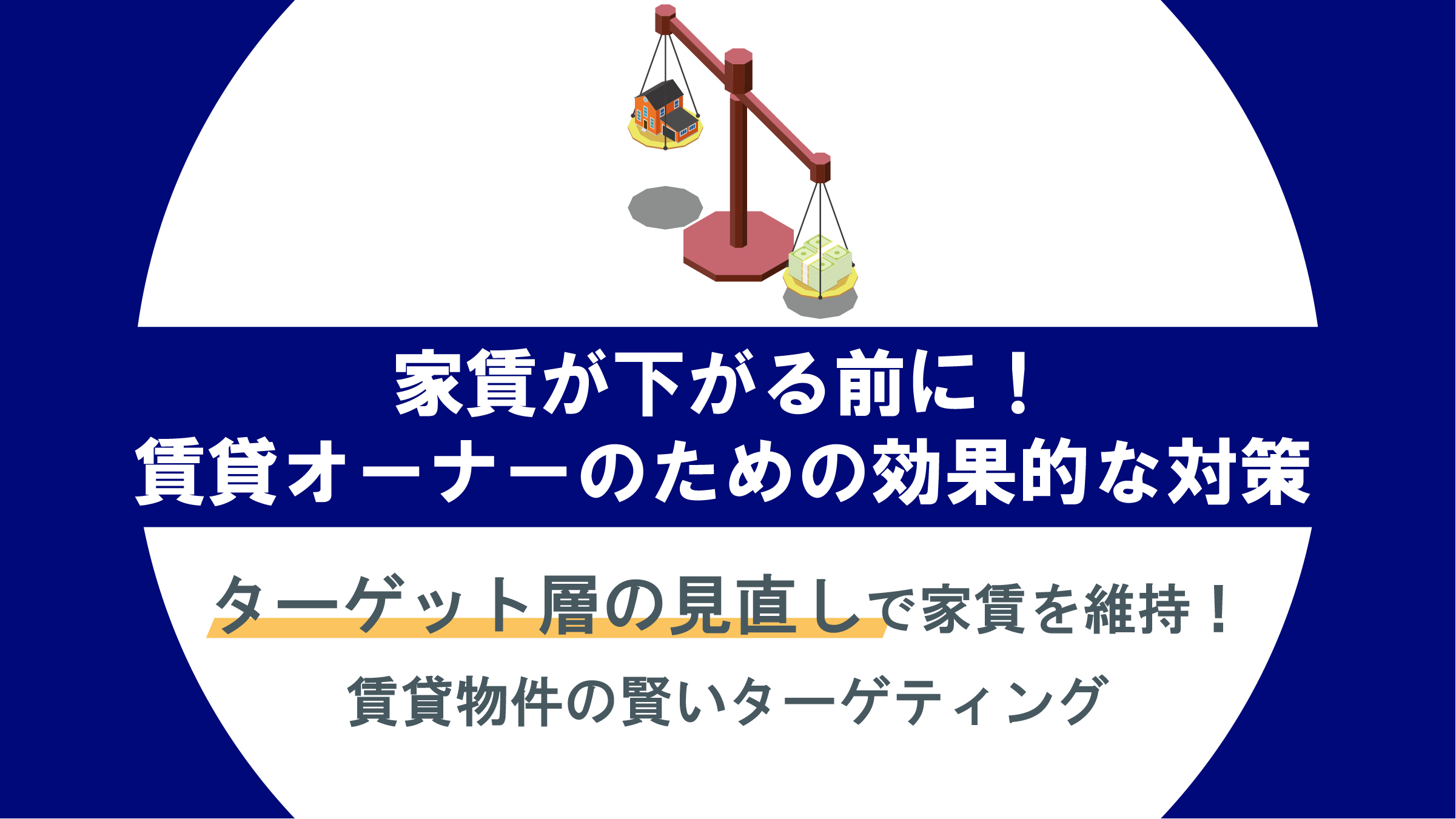
ターゲット層の見直しで家賃を維持!賃貸物件の賢いターゲティング戦略
賃貸物件を管理している大家さんや不動産オーナーにとって、家賃を維持することは一つの大きな課題です。賃貸市場は常に変動しており、特に需要の変化や地域の特性によって、物件の家賃は影響を受けます。そのため、ターゲット層の見直しは、家賃を安定させるために非常に重要です。この記事では、ターゲット層を再評価し、賃貸物件の管理における賢いターゲティング戦略を解説します。
詳しく見る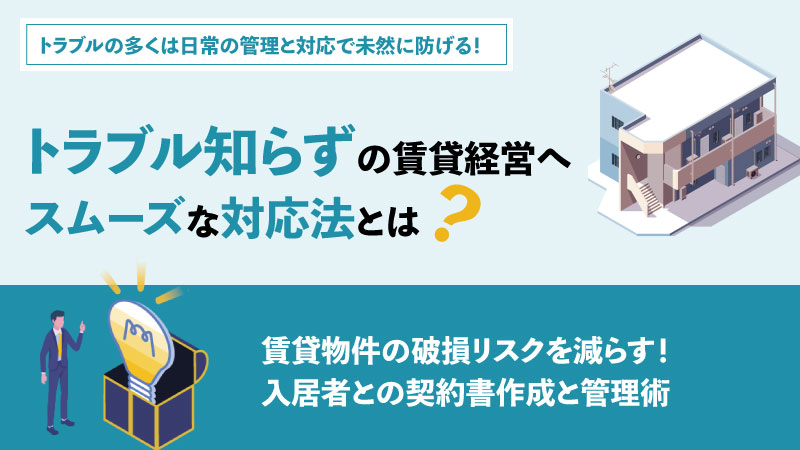
〔オーナーのためのトラブル対策ガイド⑤〕賃貸物件の破損リスクを減らす!入居者との契約書作成と管理術
賃貸物件の破損リスクは、賃貸経営における重要な課題の一つです。
詳しく見る
入居者が物件を適切に使用しない場合、壁や床の傷、設備の故障、家具の損傷などが発生し、修繕費がかさむことがあります。
これを未然に防ぐためには、入居者との契約書作成と日常的な管理が鍵となります。
本記事では、賃貸物件の破損リスクを減らすための契約書作成のポイントと効果的な管理術について詳しく解説します。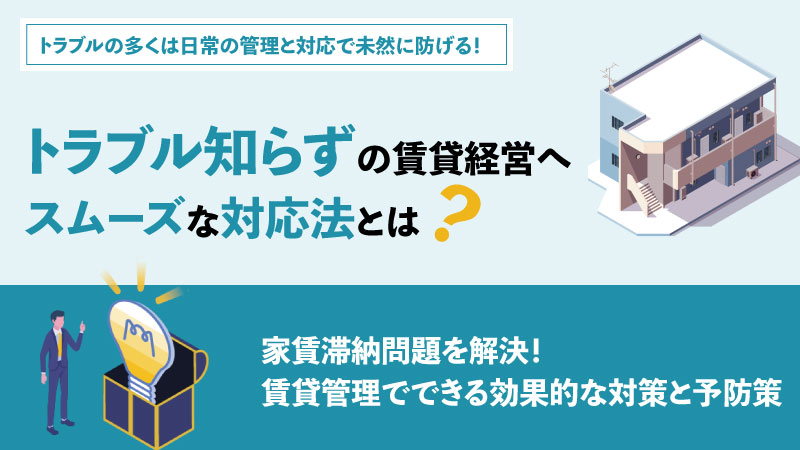
〔オーナーのためのトラブル対策ガイド④〕家賃滞納問題を解決!賃貸管理でできる効果的な対策と予防策
賃貸物件を運営する上で、家賃滞納は最も悩ましい問題の一つです。
詳しく見る
家賃滞納が発生すると、安定した収入が得られなくなるだけでなく、場合によっては法的手続きが必要になることもあります。
しかし、適切な管理と対策を講じることで、家賃滞納のリスクを大幅に減らすことができます。
本記事では、家賃滞納を防ぐための予防策から、滞納が発生した際の効果的な対処法まで、賃貸管理における実践的な方法を解説します。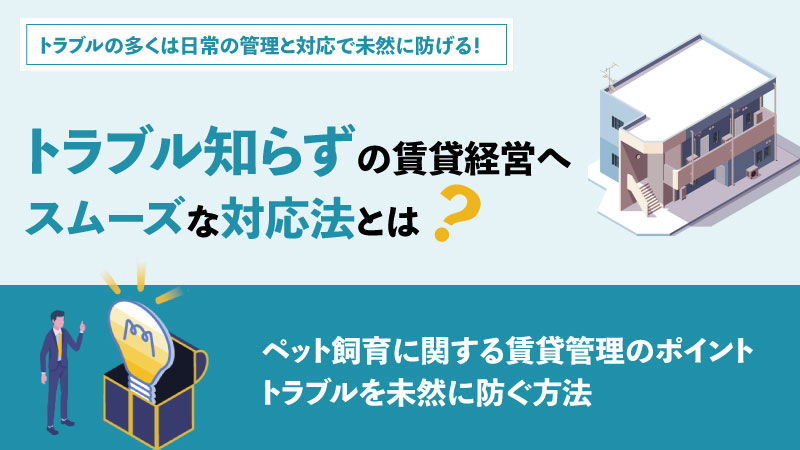
〔オーナーのためのトラブル対策ガイド③〕ペット飼育に関する賃貸管理のポイント:トラブルを未然に防ぐ方法
近年、賃貸物件でペットを飼う入居者が増えており、ペット飼育のルールをどう設定するかが賃貸管理者にとって重要な課題となっています。
詳しく見る
ペットは愛される存在である一方、騒音やにおい、破損などのトラブルを引き起こす可能性があり、これを未然に防ぐためには適切な管理が欠かせません。
本記事では、賃貸管理におけるペット飼育に関するポイントと、トラブルを防ぐための方法について詳しく解説します。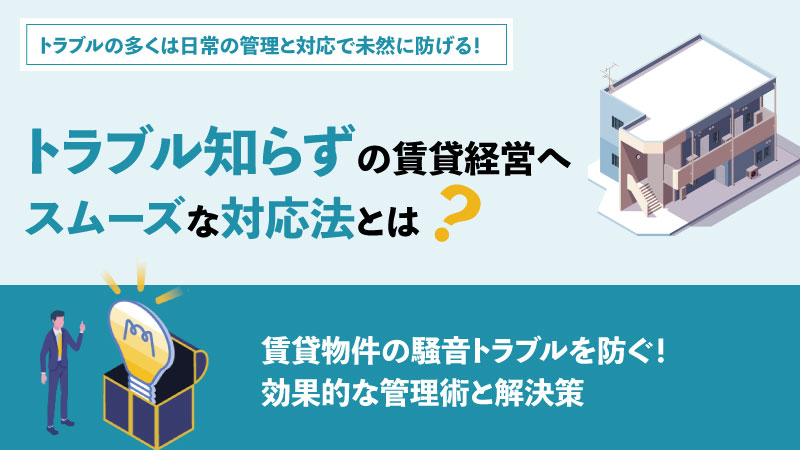
〔オーナーのためのトラブル対策ガイド②〕賃貸物件の騒音トラブルを防ぐ!効果的な管理術と解決策
賃貸物件における騒音トラブルは、入居者同士の不満を引き起こす原因となり、最終的には契約解除や物件の評判低下を招く可能性があります。
詳しく見る
特に、共同住宅やアパートなどで生活する場合、騒音問題は避けがたいものです。
しかし、適切な管理と事前対策を行うことで、騒音トラブルを未然に防ぐことができます。
本記事では、賃貸物件における騒音トラブルを防ぐための効果的な管理方法や解決策について詳しく解説します。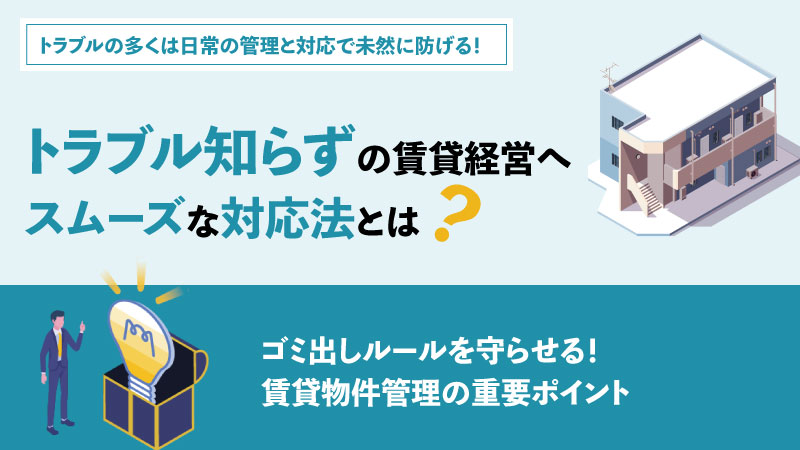
〔オーナーのためのトラブル対策ガイド①〕ゴミ出しルールを守らせる!賃貸物件管理の重要ポイント
賃貸物件の管理において、入居者によるゴミ出しルール違反は大きな問題となることが少なくありません。ゴミの放置や分別ミスが発生すると、建物周辺の環境悪化だけでなく、他の入居者からのクレームにもつながり、物件の評判を落としかねません。
詳しく見る
この記事では、賃貸管理におけるゴミ出し問題の重要性、トラブル事例、そしてゴミ出しルールを守らせるための具体策について詳しく解説します。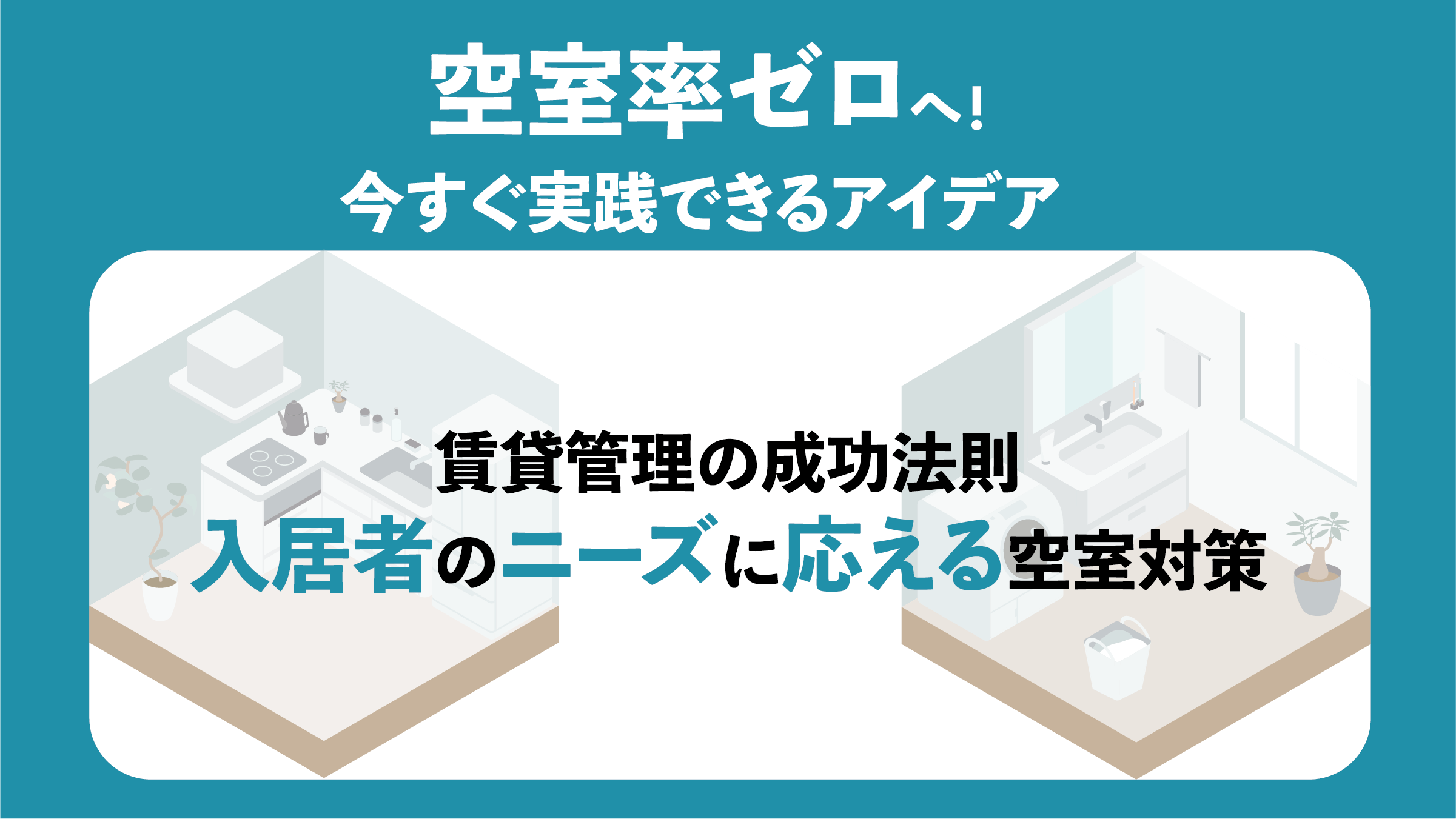
〔オーナーのための空室対策実践ガイド⑩〕賃貸管理の成功法則!入居者のニーズに応える空室対策
賃貸管理において、空室問題は最も大きな悩みのひとつです。
詳しく見る
賃貸物件を管理するオーナーや管理会社にとって、空室期間の長期化は収益に直結する大きなリスクとなります。
そこで重要になるのが、入居者のニーズを的確に捉えた空室対策です。
本記事では、賃貸管理のプロが実践する「成功する空室対策」について、入居者目線に立った具体的な施策を徹底解説していきます!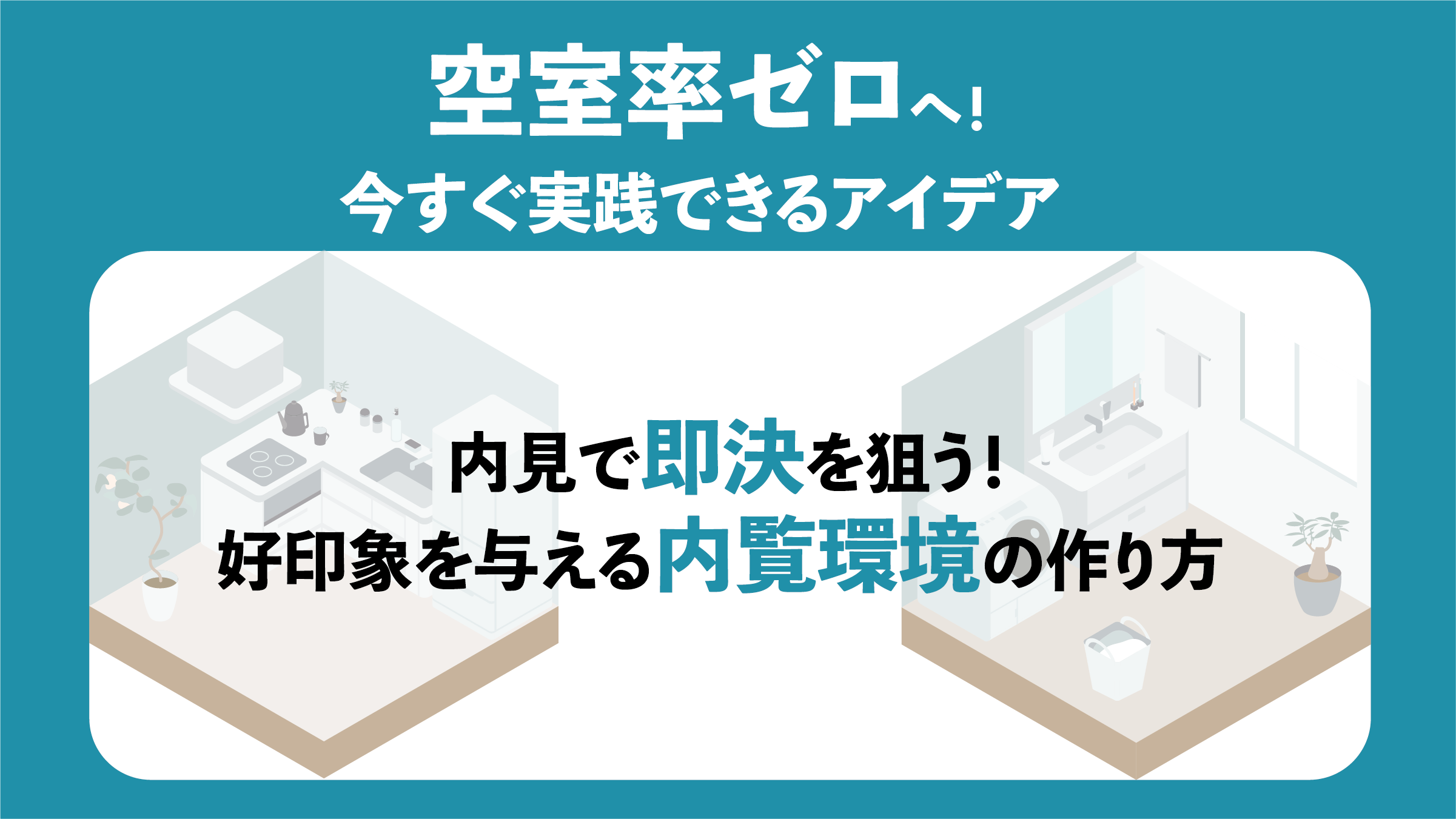
〔オーナーのための空室対策実践ガイド⑨〕内見で即決を狙う!好印象を与える内覧環境の作り方
賃貸管理において、空室対策の最も重要なタイミングの一つが「内見(内覧)」です。
詳しく見る
内見は、入居希望者が物件を直接見て、住むかどうかを判断する最初で最大のチャンス。
ここで良い印象を与えることができれば、即決に繋がる可能性がぐっと高まります。
この記事では、内見時に「この物件に住みたい!」と思わせるための内覧環境の作り方を徹底解説します!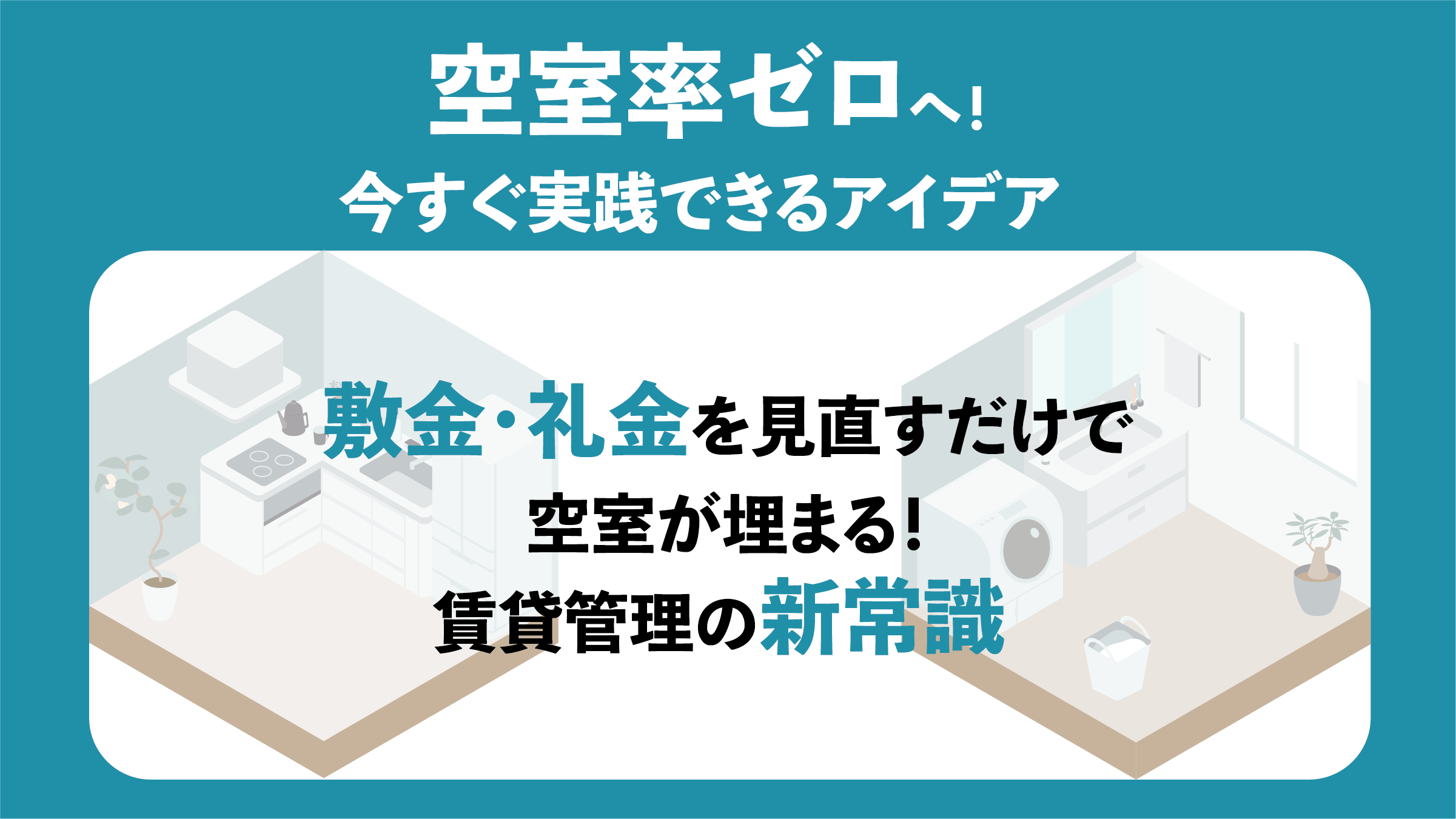
〔オーナーのための空室対策実践ガイド⑧〕敷金・礼金を見直すだけで空室が埋まる!賃貸管理の新常識
賃貸物件を管理しているオーナーや管理会社にとって、空室対策は常に頭を悩ませる問題です。
詳しく見る
近年、賃貸市場の競争が激化する中で、単なる家賃の値下げだけでは空室を埋めるのが難しくなっています。
そんな中、注目されているのが「敷金・礼金の見直し」です。
この記事では、賃貸管理における新しい空室対策の切り札として、敷金・礼金をどう見直すべきか、詳しく解説していきます。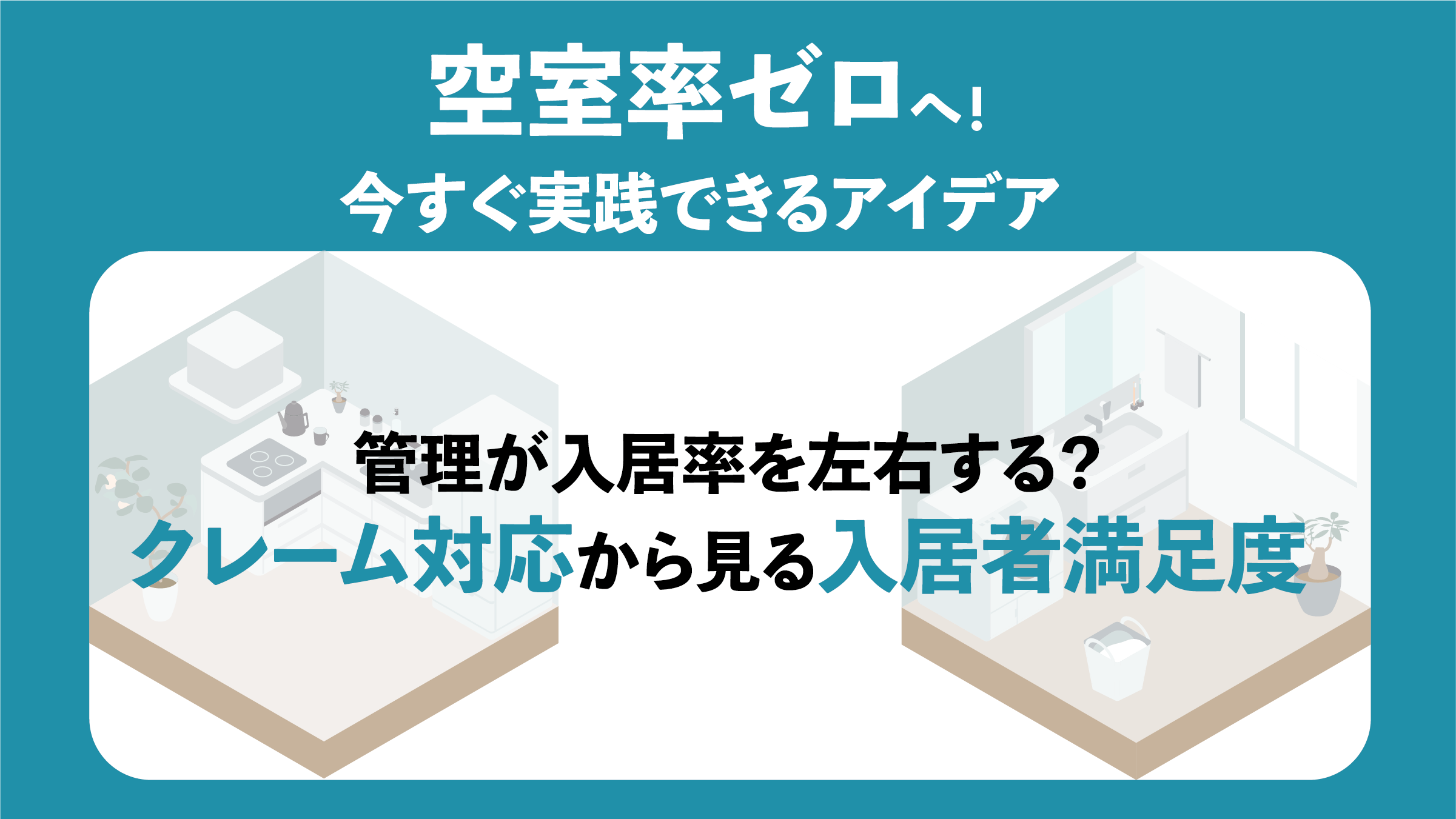
〔オーナーのための空室対策実践ガイド⑦〕管理が入居率を左右する?クレーム対応から見る入居者満足度
賃貸物件のオーナーにとって、「空室」は最も避けたい問題の一つです。
詳しく見る
いくら立地や設備が良くても、管理が行き届かず入居者の満足度が低ければ、空室が増えやすくなります。
実は、入居者が長く住み続けるかどうかは、管理会社の対応力やクレーム処理のスピードに大きく左右されます。
この記事では、管理の質がなぜ入居率に影響を及ぼすのか、クレーム対応を中心に考え、オーナーとして取り組むべきポイントを解説します。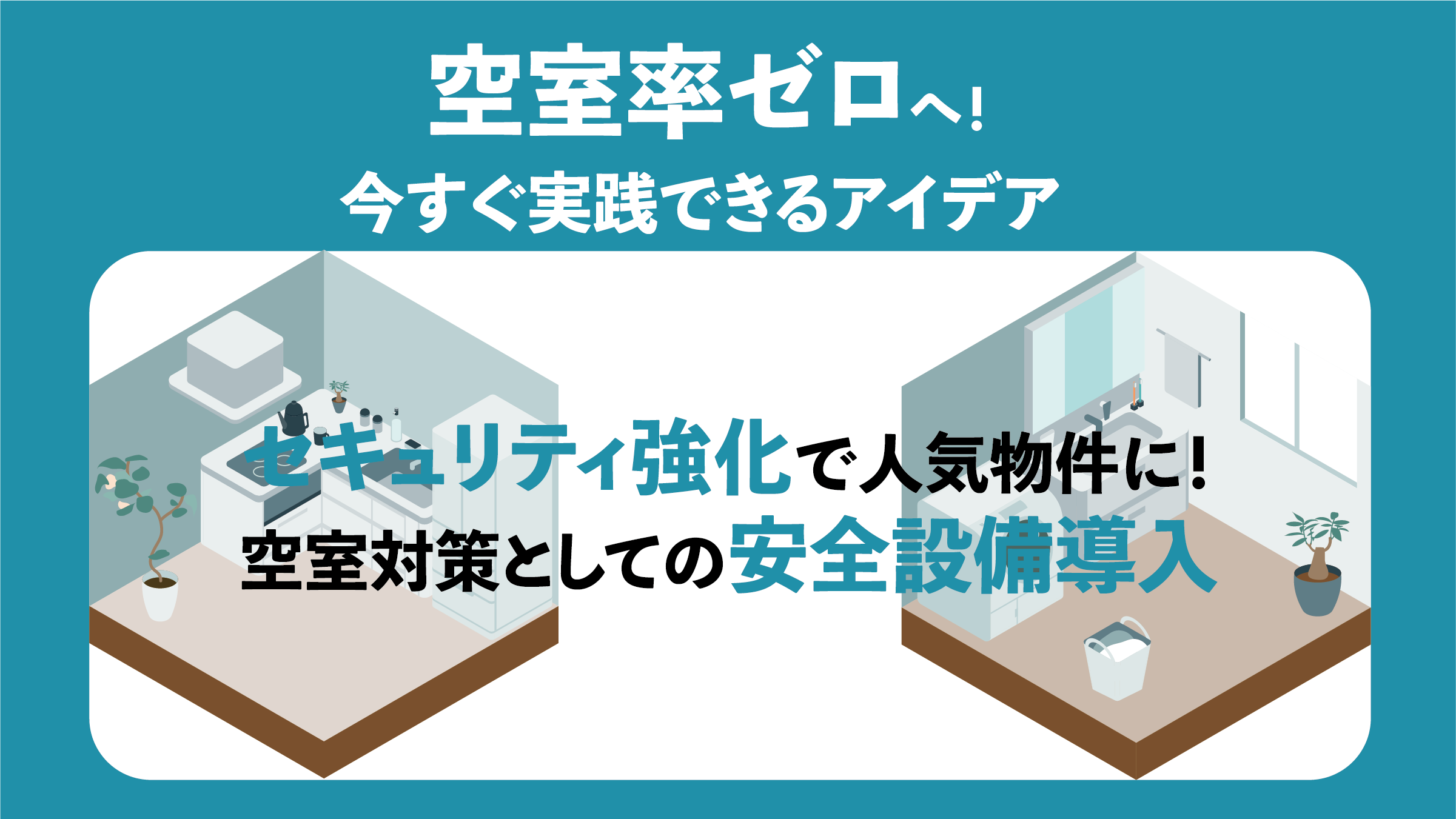
〔オーナーのための空室対策実践ガイド⑥〕セキュリティ強化で人気物件に!空室対策としての安全設備導入
賃貸物件の管理において、空室対策は非常に重要な課題の一つです。
詳しく見る
近年、入居者が物件を選ぶ基準として、「セキュリティの充実度」がますます重視されるようになっています。
この記事では、賃貸管理における空室対策の一環として、「セキュリティ強化」の必要性と、その具体的な方法について詳しく解説していきます。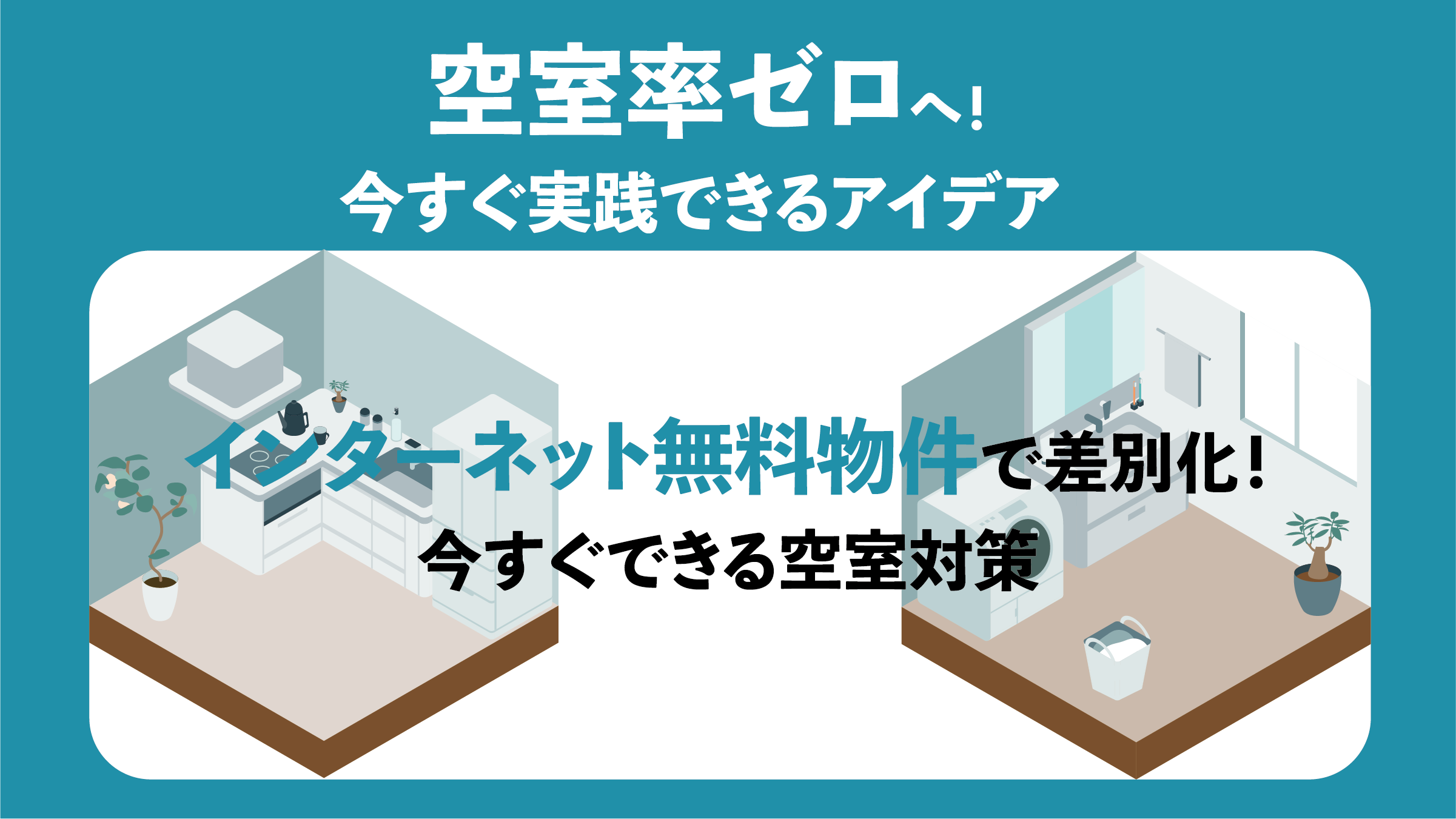
〔オーナーのための空室対策実践ガイド⑤〕インターネット無料物件で差別化!今すぐできる空室対策
スマホやパソコンが生活必需品となった現代において、インターネット無料物件へのニーズは年々高まっています。
詳しく見る
実際に「インターネット無料」だけで物件を探す入居希望者も増加しており、空室対策においても強力な武器になります。
この記事では、インターネット無料物件化のメリット、導入方法、注意点について詳しく解説します。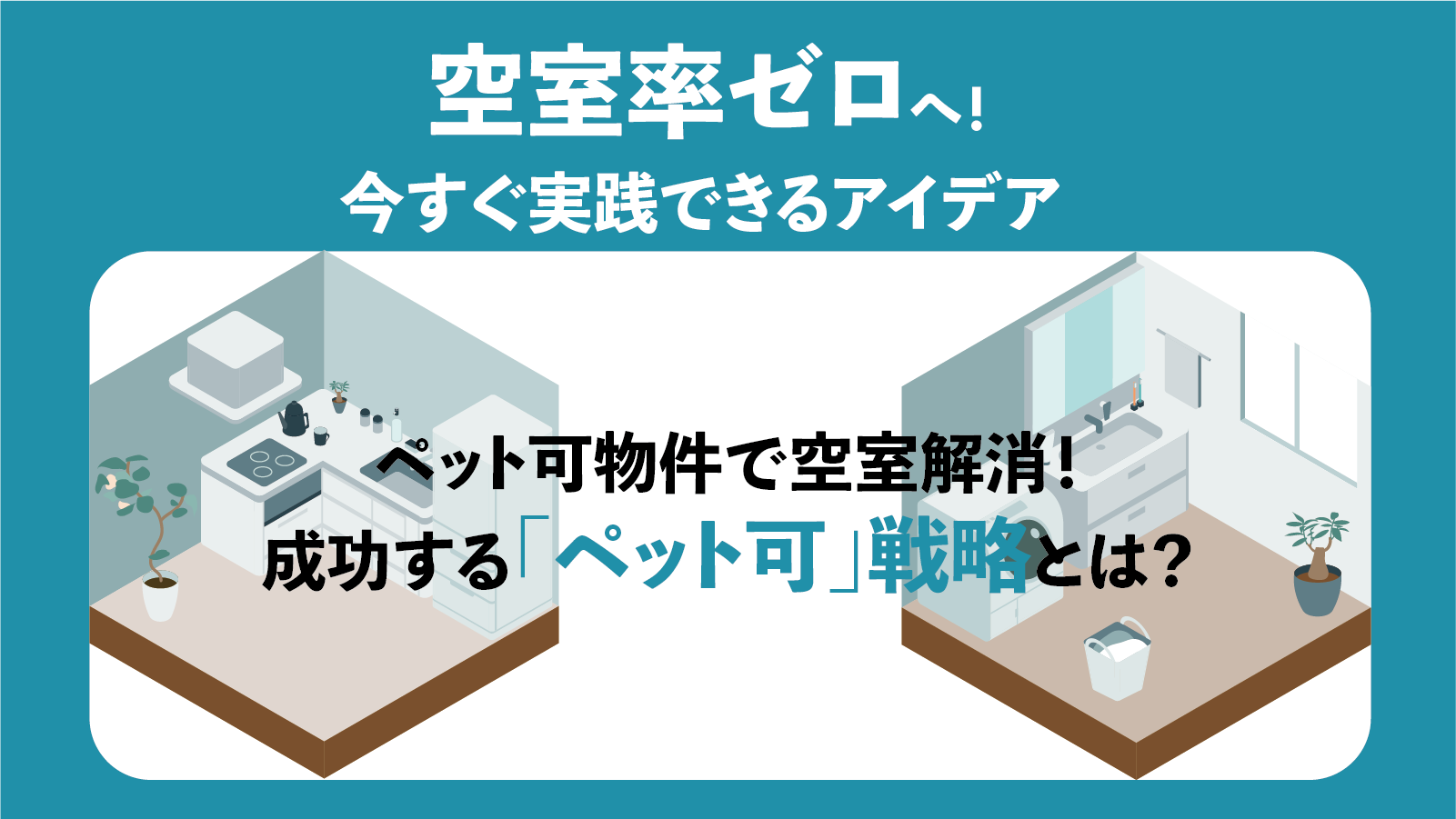
〔オーナーのための空室対策実践ガイド④〕ペット可物件で空室解消!成功する「ペット可」戦略とは?
近年、ペットを飼う世帯の増加により、ペット可物件のニーズが急上昇しています。
詳しく見る
しかし、ペット可にするだけでは必ずしも空室解消につながりません。
成功するためには、戦略的な条件設定や設備対応が欠かせません。
この記事では、ペット可物件化による空室対策の具体的な方法を詳しく解説します。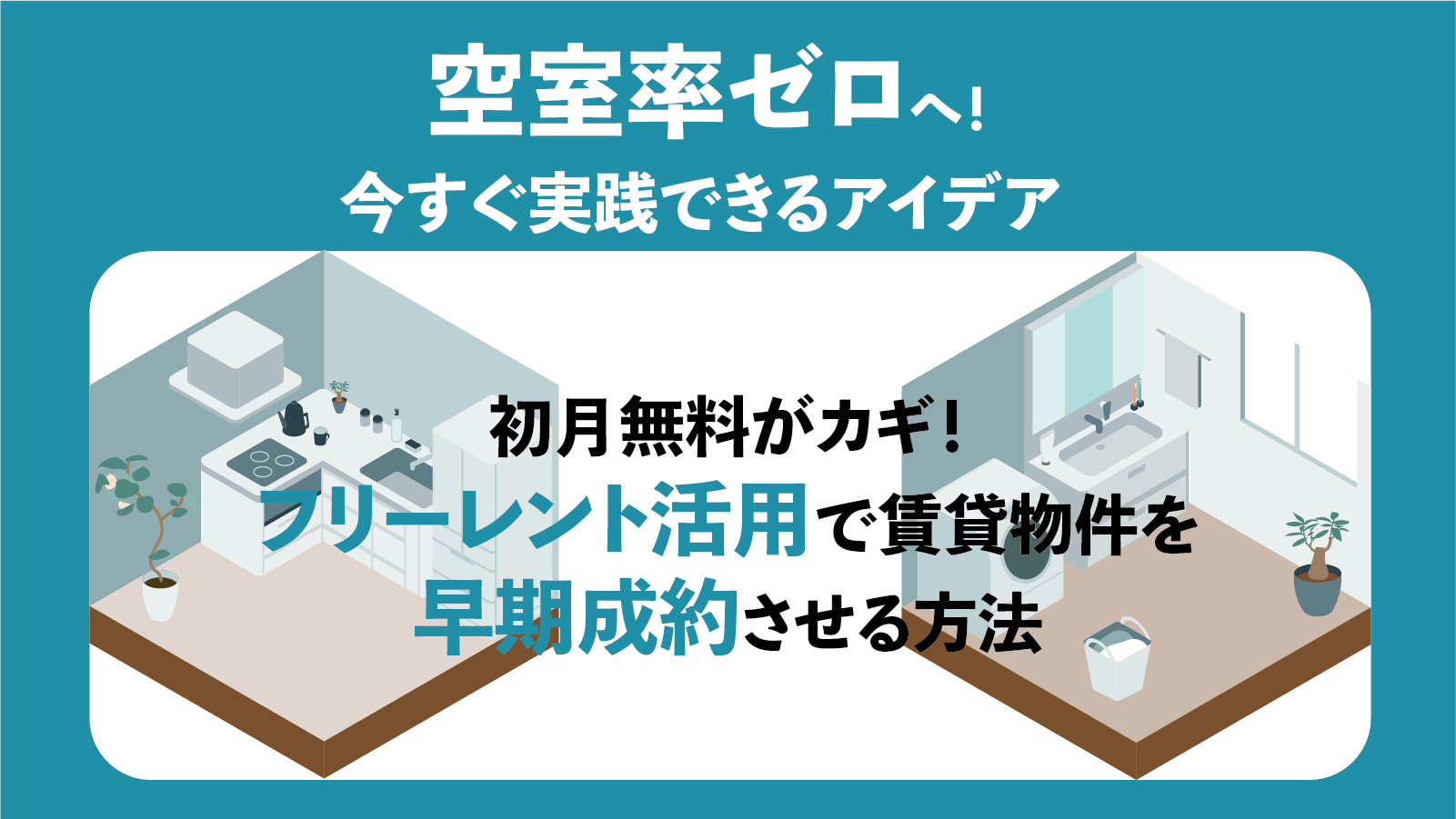
〔オーナーのための空室対策実践ガイド③〕初月無料がカギ!フリーレント活用で賃貸物件を早期成約させる方法
賃貸物件の空室が続くと、オーナーにとっては大きな損失です。
詳しく見る
そんな時、フリーレント(家賃無料期間の設定)は、入居希望者の初期負担を軽減し、スムーズな成約へと導く強力な武器になります。
今回は、フリーレントを効果的に活用する方法と、注意点について詳しく解説していきます。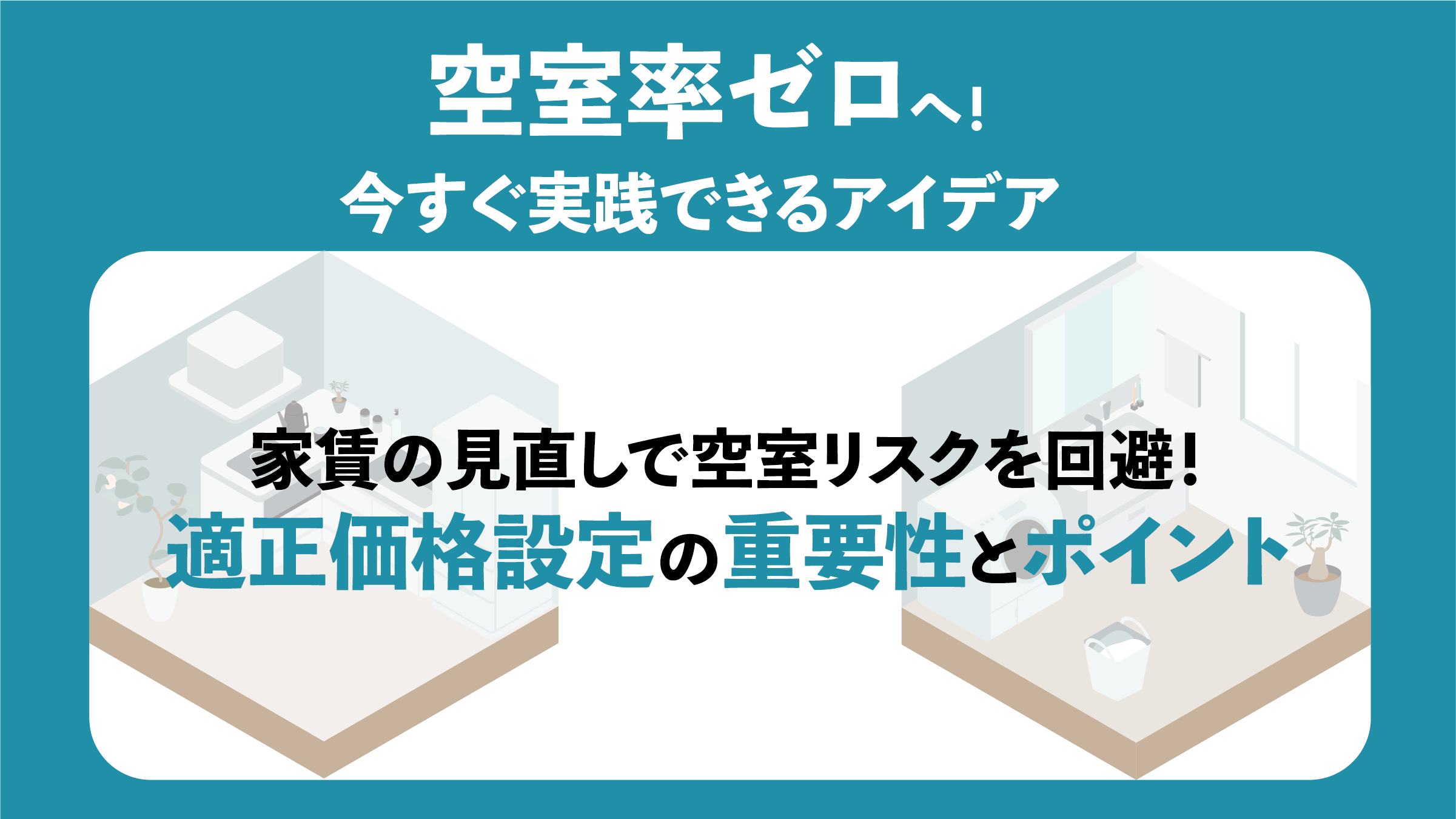
〔オーナーのための空室対策実践ガイド②〕家賃の見直しで空室リスクを回避!適正価格設定の重要性とポイント
賃貸経営において空室は最大のリスクです。
詳しく見る
内装や設備が整っていても、家賃設定が適正でないと、入居希望者の目に留まらず、いつまでも空室が埋まらない状況に陥ることも。
今回は、家賃の適正設定をテーマに、空室を防ぐためのポイントや注意点について詳しく解説します。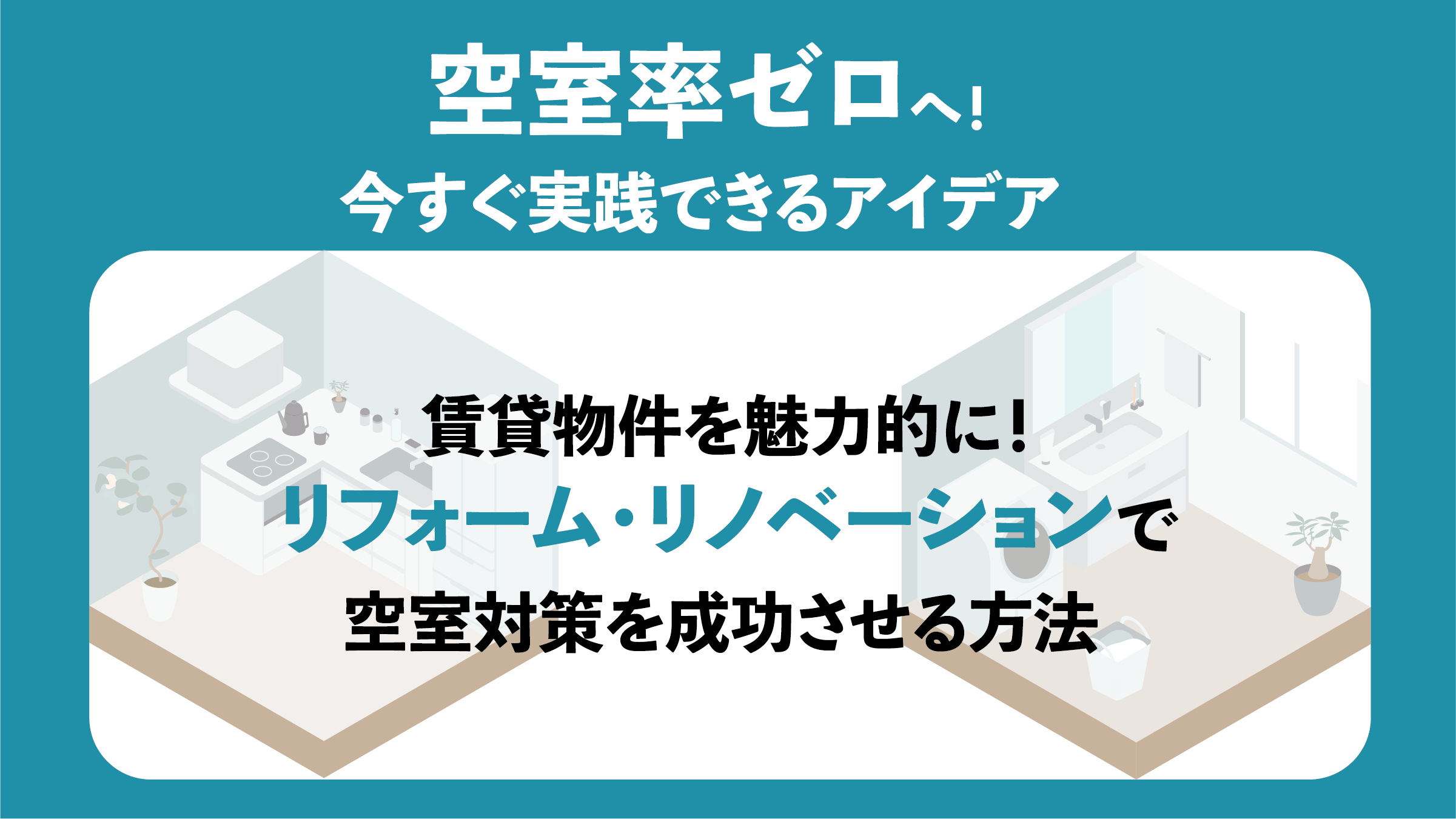
〔オーナーのための空室対策実践ガイド①〕賃貸物件を魅力的に!リフォーム・リノベーションで空室対策を成功させる方法
賃貸経営において、空室リスクの最小化は最重要課題です。
詳しく見る
築年数が経過するにつれ、どうしても物件の競争力は低下していきます。
そんな中、リフォームやリノベーションは、物件の魅力を取り戻し、空室期間を短縮するための有効な手段となります。
この記事では、リフォーム・リノベーションを空室対策にどう活用すべきか、具体的な方法とポイントを解説していきます。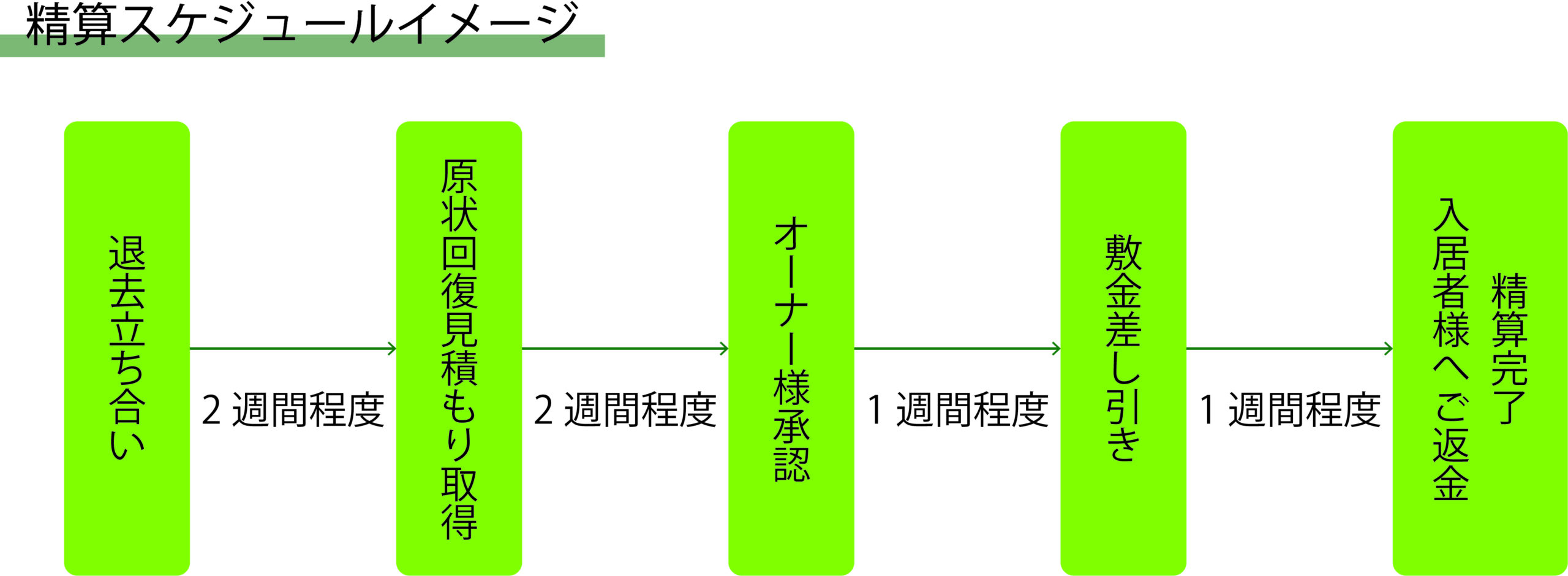

管理内容と管理プラン
ウルクルではオーナー様の理想の賃貸経営を実現するために、管理において「こうしてほしい」「これはしなくていい」というご要望を伺い、お一人お一人、また物件ごとに管理サービスをカスタマイズしております。
詳しく見る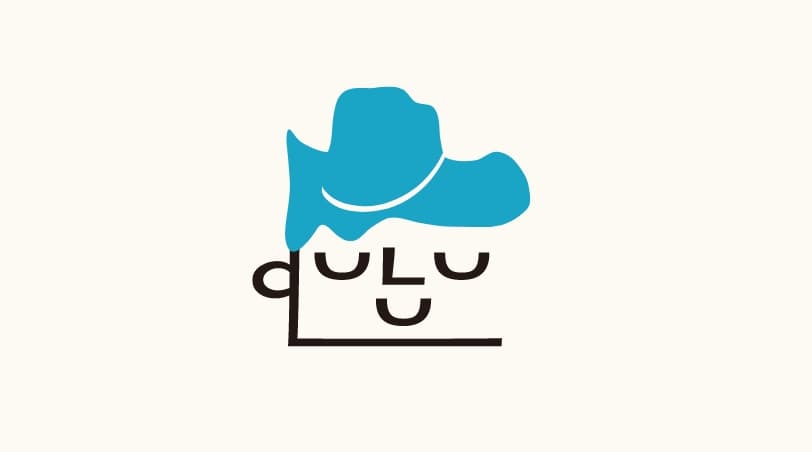
定期借家契約とは?
賃貸物件をお探しの方に向けて、定期借家契約の活用方法をご紹介します。
詳しく見る
定期借家契約には様々なメリットがあり、賃貸経営の選択肢として活用できるでしょう。
本記事では、定期借家契約の概要から活用ポイントまで、賃貸物件をお探しの方の課題解決に役立つ情報をお届けします。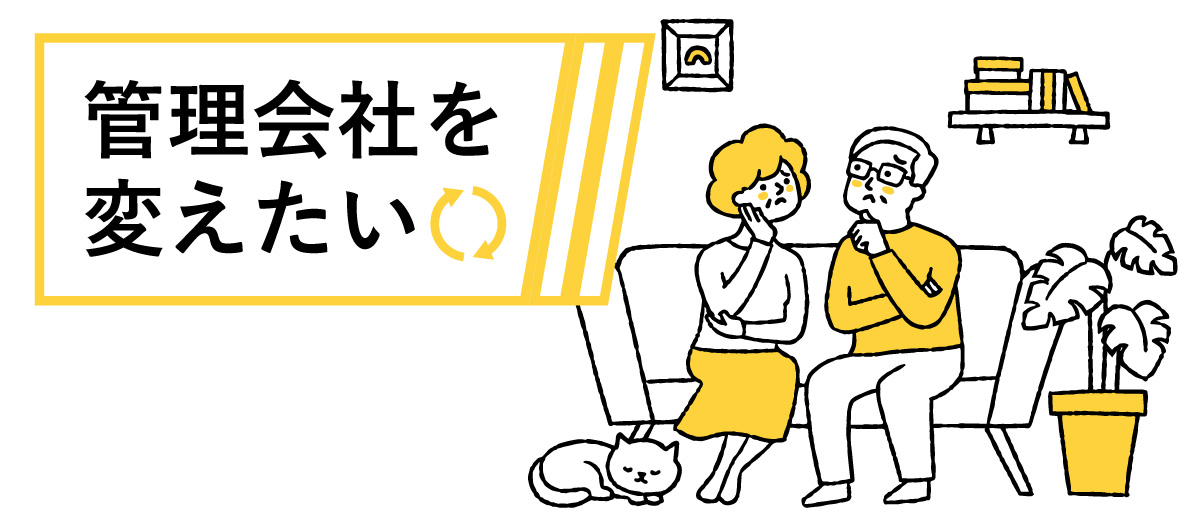
管理会社を変えたい
空室がなかなか埋まらない、入居者トラブルが多い、収益率を向上させる提案がないなど、管理会社に不満を持つようなことがあれば、管理会社の変更を検討するタイミングなのかもしれません。
詳しく見る
ただ建物管理もお願いしていたり、契約期間が残っているとすぐに切り替えることができないので、まずは現状の課題を整理する意味でも、いろいろな管理会社の話を聞いてみるところから始めるのもよいでしょう。
弊社では、賃貸経営のサポートをさせていただく際に大事にしていることが、『担当者との関係性』と『営業力』です。賃貸経営は日常的に続くものだからこそ気持ちのよいやり取りが必要ですし、仕事にコミットする『営業力』があってはじめてオーナー様との関係性も強固なものになると考えています。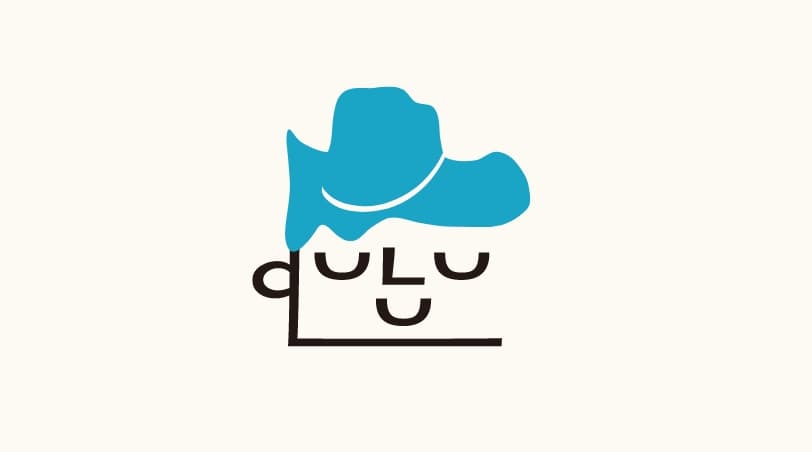
物元が複数いる場合に注意すること
1社に専任媒介で任せるよりも、一般媒介で複数社に募集をお願いしたほうが早く決まるだろう。そう考えて物元の管理会社を増やされるオーナー様はたくさんいらっしゃいます。しかし、複数社に任せるにあたって、一定の制限をかけることが早く決まるコツでもあります。
詳しく見る
例えば、物元には下記のようにお願いをします。
①ポータルサイトへの掲載は物元だけにしてほしい
②仲介さん(2次募集先)は自社ホームページだけで広告してほしい
③更新事務手数料は(取ってもいい・取らないでほしい)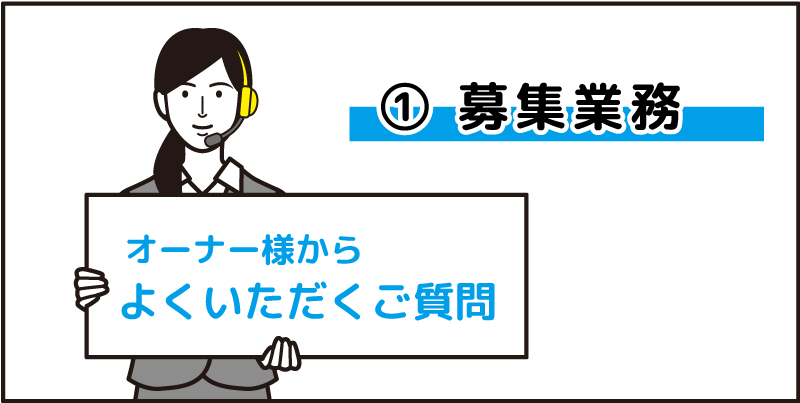
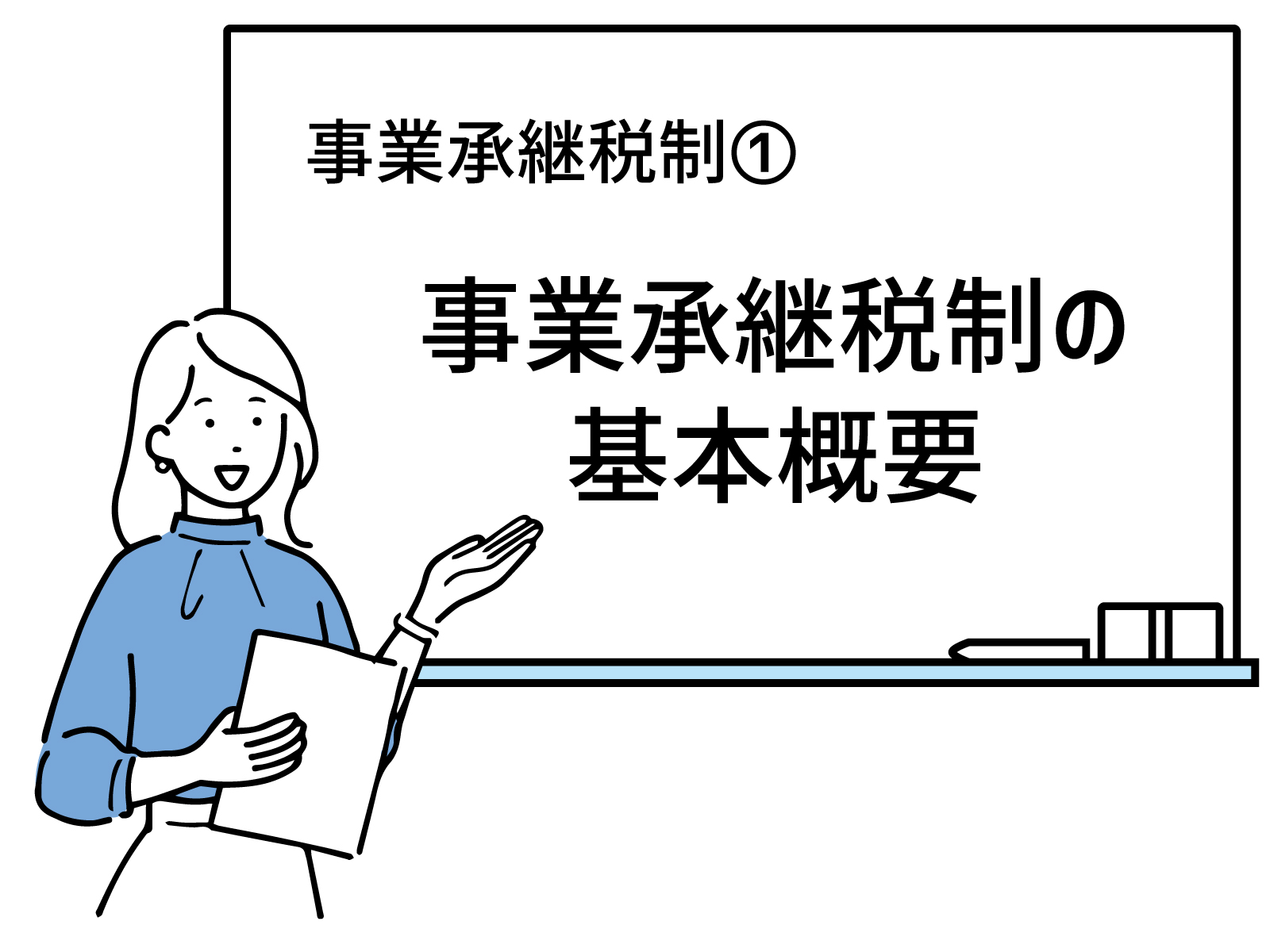
①事業承継税制の基本概要
事業承継税制とは、事業承継をする際に発生する贈与税や相続税などを猶予または免除してもらえる制度のことです。
詳しく見る
事業承継税制の最大のポイントは「免税」でもなく「非課税」でもなく「納税猶予」だということです。(将来的に免除されることを想定しています)
中小企業庁によって定められた要件を満たし認定されることが前提となりますが、大幅に税負担を軽減させることができるので経営上大きなメリットがあります。
贈与税・相続税は累進課税のため、受け継いだ資産が現金であればそれを利用して税金を払えますが、株式はそのままでは支払うことができません。
場合によっては事業を継続する資金が納税によってほとんどなくなってしまう事態も起こりかねません。
お金の工面が難しい場合や、事業承継に関する苦労が重すぎることで後継者が見つからず廃業になってしまっては雇用が失われてしまいます。
納税負担を軽減させることで、中小企業の継続的な経営を支援すべく設けられたのが事業承継税制です。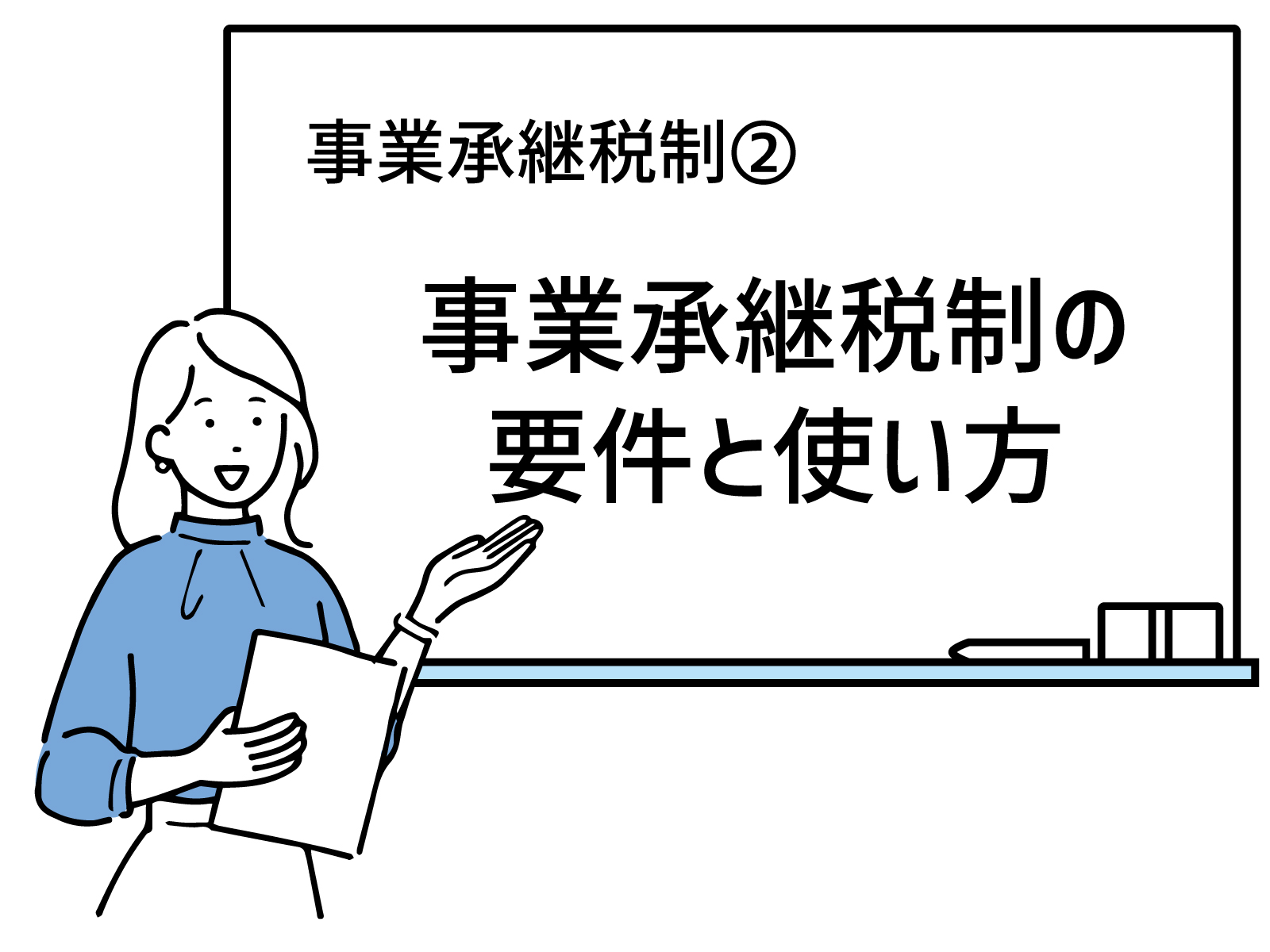
②事業承継税制の要件と使い方
詳しく見る
事業承継税制においては、対象となる企業や経営者に認定要件を設けています。
まずはそれぞれの要件に当てはまるかの確認が必要です。
【先代経営者の主な要件】
・会社の代表者であったことがある
・贈与(相続)直前で、一族の中で筆頭株主で総議決権数の過半数を保有していたこと
先代経営者から後継者への贈与は、基本的には先代経営者が持つ株の全株を贈与しなければなりません。
また、先代経営者は、贈与時には代表を退任している必要があります。
【後継者の主な要件】
・生前贈与・相続により、筆頭株主となり総議決権の過半数を保有していること
[贈与の場合]
・贈与直前に3年以上役員であったこと
・贈与時に代表取締役になること
[相続の場合]
・相続直前に役員であったこと
・相続開始から5か月以内に代表取締役になること
後継者は、先代経営者の家族や親族でない第三者でも適用可能です。
ただ、家族のときよりも、注意点も多くなります。
また一般措置で納税猶予の対象となる後継者は1名のみですが、特例措置では最大3名まで認められます。
※一般措置と特例措置について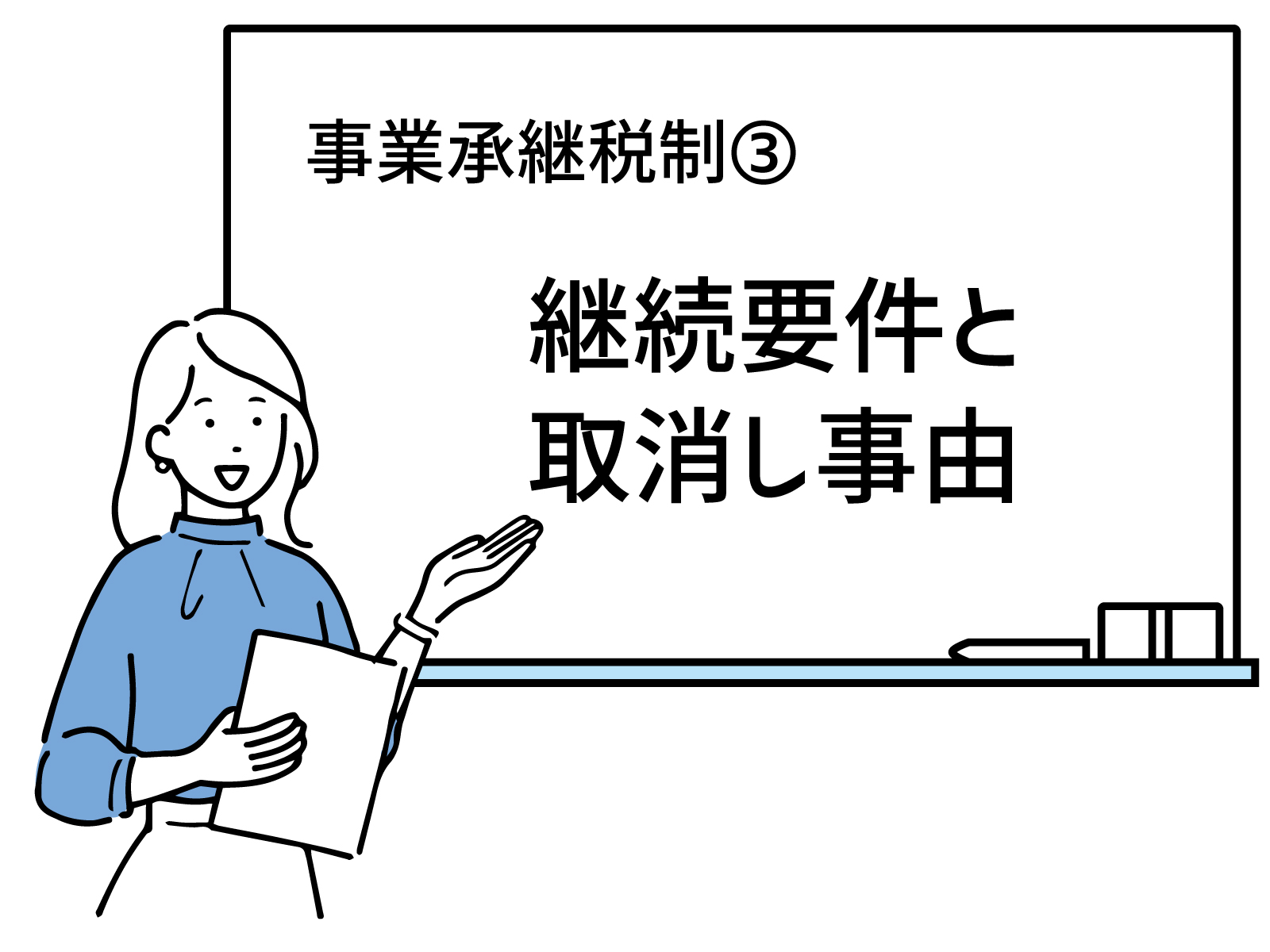
③納税猶予の継続要件と取消し事由
詳しく見る
この制度は要件を満たし、認定されて終わりではなく、認定された後でも5年間継続が求められる要件があります。
取り消されると猶予税額と利息の納付が必要になります。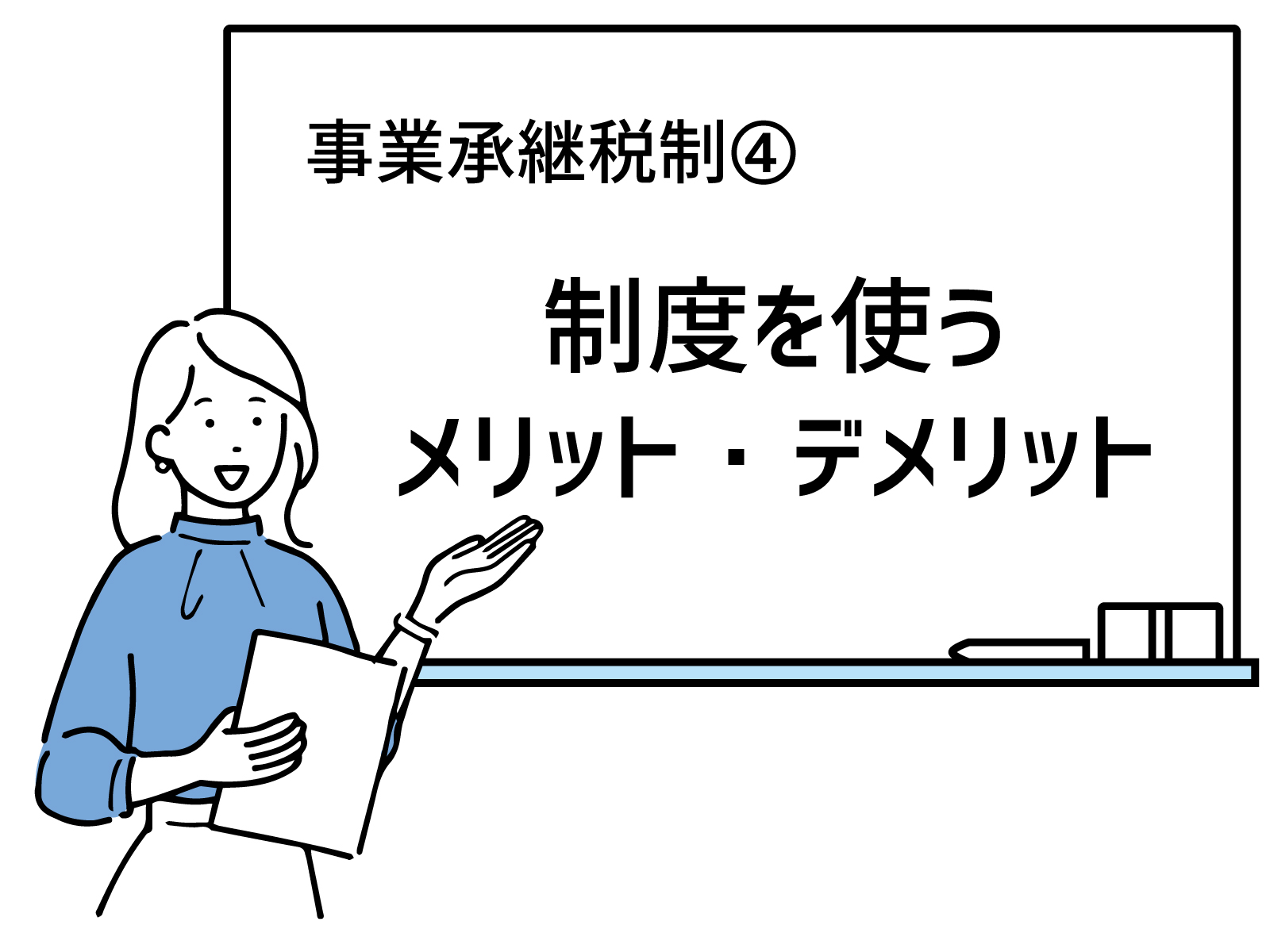
④事業承継税制を使うメリットとデメリット
詳しく見る
事業承継税制はメリットの多い税制ですが、いくつかのデメリットもあるので注意が必要です。
[メリット]
・事業承継にかかる税金が大幅に猶予・免除される
猶予された税額は後継者の相続発生など、一定の事由が発生することで免除され、将来的に対象株式の贈与税・相続税の負担がゼロになります。
・納付予定だった税金を事業資金に回せる
贈与・相続に伴う現金を準備する必要がなく、事業資金に回すことができます。
[デメリット]
・毎年(または3年に1回)の届け出を忘れると猶予が終了する
最初の5年経過後は継続届け出の提出が3年に1回になるため、失念してしまった場合は猶予期間は終了となり納税が確定されます。
専門家に依頼している場合は別として、大半を自身で行う際は注意が必要です。
・取消し事由に該当すると税額+利子が発生する
無事事業承継税制が開始したとしても、取消し事由に該当すると、これまで猶予されていた贈与税や相続税に加えて利子税も支払わなくてはいけなくなります。
ただし業績悪化などで事業売却・廃業した場合においては、業績悪化後の自社株評価額により再計算されるため、税負担としては軽減することができます。
・専門家の知識が必要
複雑な制度の上自部手続きや準備する書類も煩雑なため、また特例措置の「特例承継計画の提出」においては専門家のサポートが必須になっているため、継続的に依頼をしないといけません。
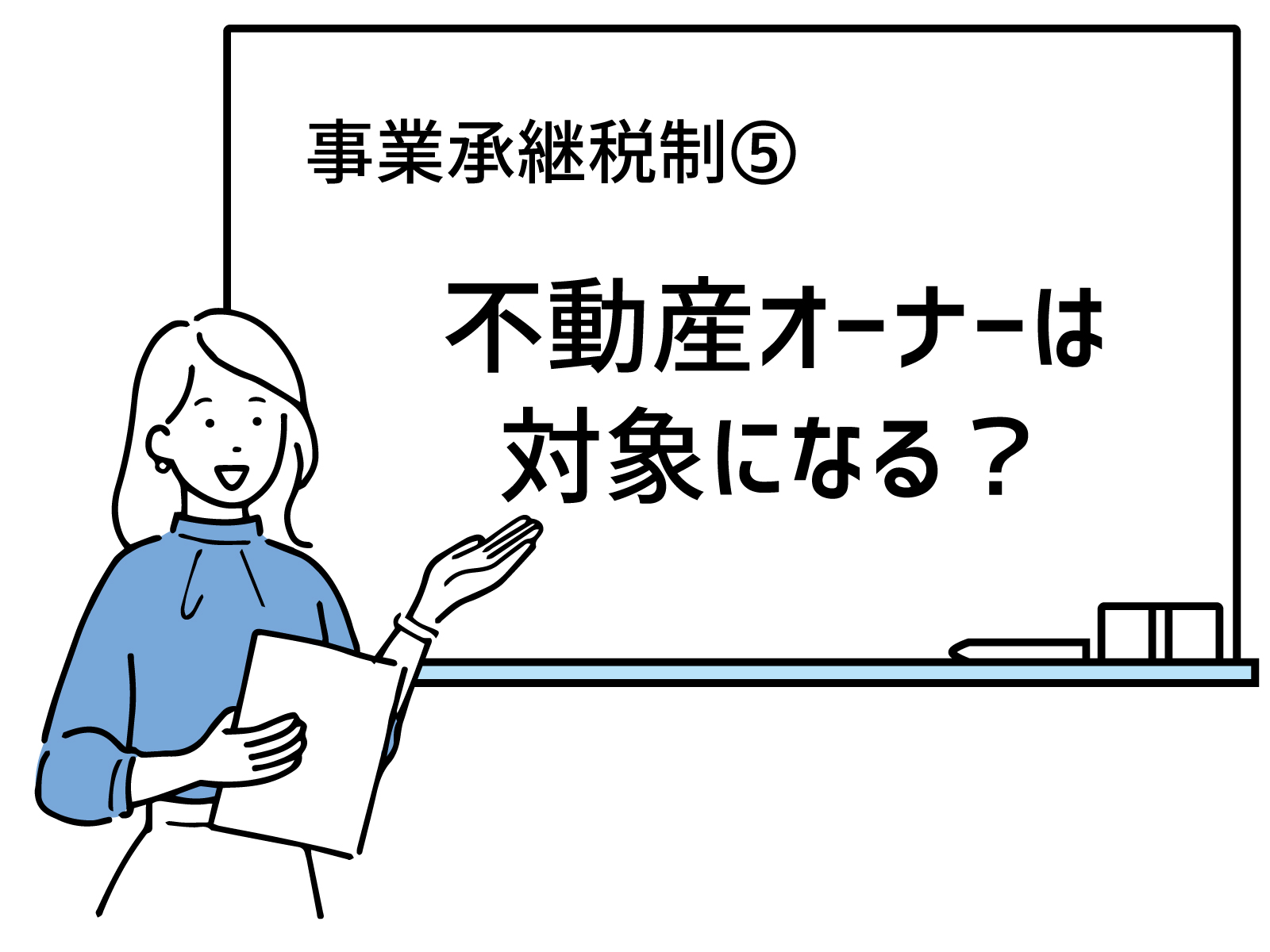
⑤不動産オーナーは対象になる?
詳しく見る
個人事業主としての事業用資産が対象の個人版事業承継制度もありますが、残念ながら賃貸管理業・貸付業は対象外になるケースがほとんどです。
不動産賃貸業の多くが「事業」と見なされず、対象外となる場合が多いからです。
対象外となるのはどのような場合なのか、適用されるために必要な要件とはどのようなものなのかを解説します。
・原則的に資産管理会社には事業承継税制は適用されません。
事業承継税制が適用されるのは、あくまでも「雇用をもたらす事業」に対してです。
事業実態を伴わない会社、納税猶予を目的として設立された会社に適用するとなると、事業承継を推進するという趣旨からはずれるため対象外になります。
・資産管理会社には「資産保有型会社」と「資産運用型会社」の2つのタイプがあります。
該当する場合には原則として、新・事業承継税制が適用されません。
「資産保有型会社」の定義
「資産保有型会社」とはその名称どおり、保有している資産の7割以上を特定資産が占めている会社と定義されています。
特定資産とは自社の業務で使っていない不動産、株式や国債などの有価証券、現預金、貴金属などのことです。
建売住宅や投資用不動産などの販売用不動産も特定資産に含まれるため、資産保有型会社と判断されると想定されます。
「資産運用型会社」の定義
不動産賃貸業における「資産運用型会社」は直近の事業年度の総収入額に対して、不動産の家賃収入など、資産を運用することによって得た収入の割合が75%以上を占める会社を指します。
賃貸収入は「特定資産の運用収入の合計額」に含まれるので、賃貸収入が大きくなれば資産運用会社と判断されると想定されます。
資産運用型会社で事業承継税制が適用される例外とは?
資産管理会社は原則的には新・事業承継税制が適用されません。しかしいくつかの事業実態要件を満たすことによって適用される場合もあります。その要件とは次の三つです。
①3年以上事業を行っている
相続もしくは贈与日まで3年以上継続して事業を行っていることが新・事業承継税制が適用される一つ目の要件となります。
不動産賃貸業の場合の主な事業は不動産賃貸ということになるでしょう。子会社、グループ企業への不動産賃貸ではなくて、第三者への不動産賃貸を行っていることが要件となります。つまり雇用を創出する事業を指します。
②従業員が5人以上いる
ここでの従業員の定義では親族およびアルバイトやパートなどの非常勤は除外されます。
つまり正規の従業員が5人いることが条件となるのです。小規模の不動産賃貸業を営んでいる場合は、この要件をクリアするのは簡単ではありません。
③従業員が勤務する事業所がある
事業所は所有しているものでも賃貸でも構いません。
ただし、経営者や親族の自宅を事業所として登録している場合にはこの要件を満たしていないということになります。
3つの要件をすべて満たした場合に初めて事業実態があると認められ、新・事業承継税制の適用が可能になるのです。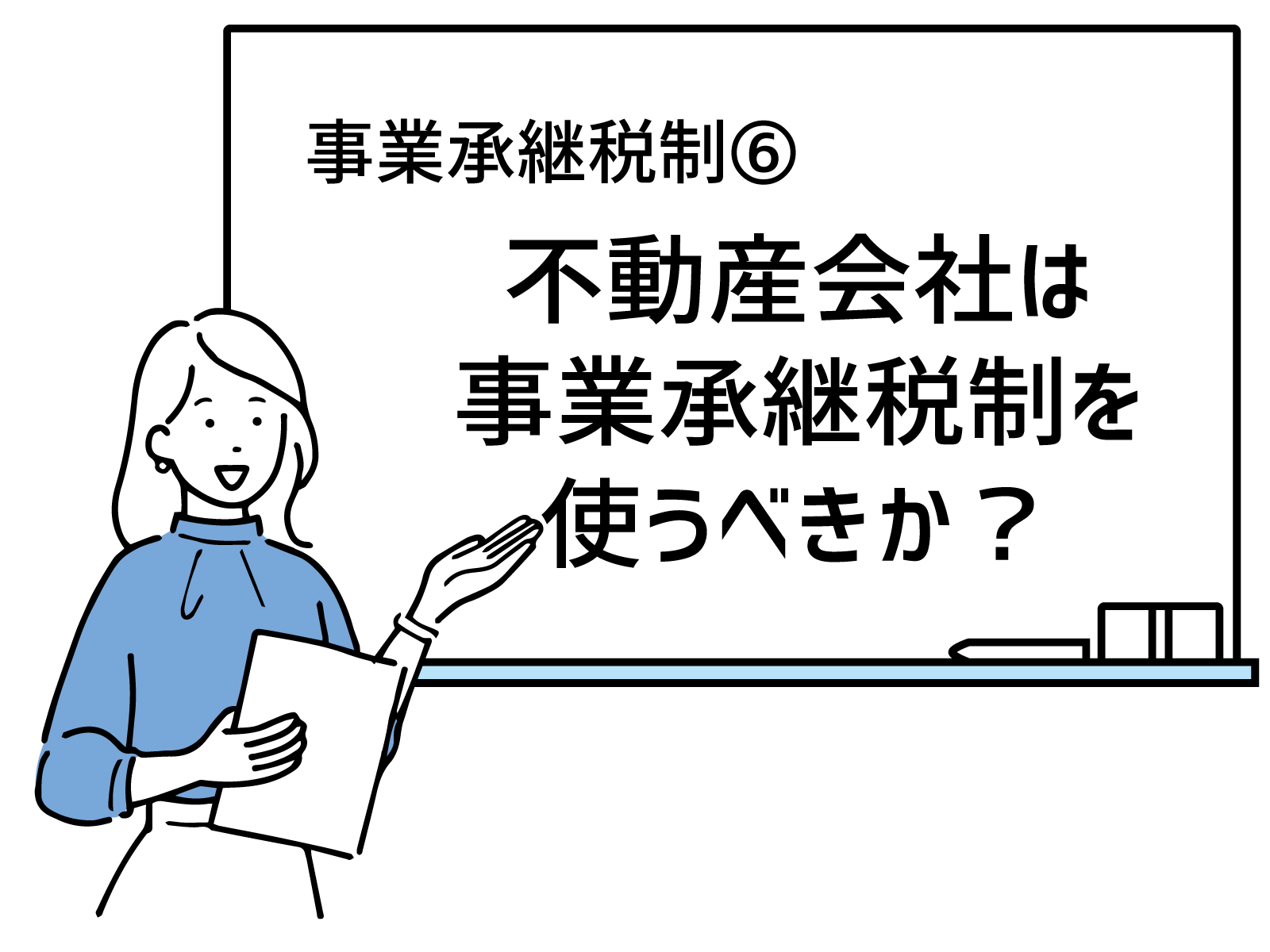
⑥不動産会社は事業承継税制を使うべきか?
不動産会社でも実業実態があり、条件を満たせば事業承継税制を使うことは可能です。
詳しく見る
ただし贈与税の納税猶予は先代の経営者がなくなるまで一定の要件を満たせばよいのですが、相続税の場合は後継者が亡くなるまで(もしくはその次の代に贈与するまで)は一定の要件を満たし続ける必要があります。
不動産会社ですと数年後・数十年後に売上高や資産に変動があり、「資産保有型会社」や「資産運用型会社」に該当してしまうこともあるかもしれません。
そうならないための方法も併せて検討する必要があり、例えば、納税猶予を適用し続けるために先代が代表取締役を退任・退職する際の退職金を現金ではなく不動産で支給し、そのあと不動産会社に貸し付けて賃貸収入を得れば、退職後の安定収入にもなりますし、結果的に所得分散による節税効果もあります。
相続税・贈与税の猶予期間は長いので、本当に適用するべきか慎重に検討する必要があります。





